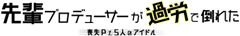
比奈、春菜、裕美、ほたるの四人はそれぞれ、美城プロダクションから走り去った茜に連絡を試みた。しかし結局応答はなく、四人は不安を抱えながらその日を終える。
翌日の日中、比奈はプロデューサールームを訪れていた。
先輩プロデューサーは比奈を快く招き入れる。
応接セットのテーブルの上には一枚の書類が置かれていた。
「見てよ、それ」先輩プロデューサーは比奈に書類を示す。「人事に聞いたら見つかったんだ、日野茜さんの書類。アイツ、なぜか茜さんをアルバイトとして登録していたみたいなんだよね。ドラマのエキストラとか、ほんとに単発で終わっちゃうような仕事ならその扱いもわかるんだけど……アルバイトだと美城のデータベースには登録しないから、それでボクは茜さんを見つけることができなかったんだ」
比奈は応接セットのテーブルの上に置かれた書類を見る。茜の登録書類だった。
「アタシは正式に登録されてたんスか?」
比奈の問いに、先輩プロデューサーは頷く。
「たぶん、比奈さんはボクがもともとスカウトする予定だったから、アイツもそのまま正規の所属アイドルとして登録したんだろうね。茜さんのほうはアイツがスカウトしたから、ボクの意向を確認しようとしたのかも。もともと、このユニットはボクが立ててた企画だったからなぁ」
先輩プロデューサーは溜息をつく。
「そのことなんスけど」
比奈は、茜の書類を机に置いて、姿勢を正して真剣な表情で先輩プロデューサーを見つめる。
「今日は、お願いがあって来たっス」
年代物のレジを乗せた年代物の机、年代物の椅子、年代物の酒屋。……実家。俺は頬杖をついて、店内から外を眺めていた。幼少の頃から代わり映えしない景色、ただ俺の背が伸びるにつれて視点だけが、あの頃よりも高くなっている。高くなりきったあとは、視界が少しずつ古くなっていくだけだ。
最寄りの新幹線の駅からさらに在来線、バスと乗り継ぎ、都心の借家から片道およそ七時間。時の止まったような地元に、俺は帰ってきていた。
しばらく仕事を休むと言って急に帰ってきた俺を、両親は特に疑問を呈するでもなく受け入れてくれた。仕事を辞めて店を継ぐ話はそのうちするつもりだった。
そのまま、何事もなく二日間が過ぎた。
次の日の昼間、お袋が買い物に行くからと俺に店番を命じ、出かけて約二時間。こうしてずっと店の中から外をぼーっと眺めていた。親父は近所に将棋を指しに出かけている。
外は殆ど人も車も通らない。犬や猫のほうが多く通り過ぎるくらいだった。都会とは時間の流れ方がまるで違う。
この景色が嫌になる前に、なにか趣味か副業を見つけたほうがいいな、と俺はぼんやり考えていた。何もしないでいると、このままこの店と一緒に一気に歳をとりそうだと思った。
スマートフォンを取りだし、真っ暗なままの画面を見て、すぐにまたしまう。この場所に座ってからもうこの動作を五回ほど繰り返していた。スマートフォンをチェックするのは手癖になっている。取り出しては電源をオフにしていたことを思い出し、またしまう。ずっとこんな調子だった。
店番をしていても客が来るわけでもない。この店の主な収入は年末年始をはじめとした祝い事の注文のほかは飲食店のタンクの補充だ。俺は居間に戻り、朝刊を取ってくる。番組表を眺めた。番組編成は都会とは大きく違う。
ぼんやりと考えていた。茜たちの出演するような番組は見れるだろうか。関東ローカル局の番組は難しいだろう。ネット配信でやっていればいいのだが。
――と、そこまでを考えて、俺は新聞を畳んで置いた。
プロダクションから物理的な距離は置いた。精神的な距離も置いて、それに慣れたほうがいい。俺はもうプロデューサーではない。茜たちのことを考えられる立場ではない。……考えてはいけない。
――茜ちゃんも春菜ちゃんも裕美ちゃんもほたるちゃんも、プロデューサーは、置いていっちゃうんスか――
比奈の言葉が頭に蘇る。茜たちを置いて行った。それは決してネガティブな感情からではないが、置いて行ったことは確かだ。
比奈は俺の思惑をみんなに明かすだろうか。あいつらに、嫌われるだろうか。……嫌われるだろう。それを覚悟してやったことだ。俺は溜息をついた。覚悟してやったはずなのに、俺の頭からは五人の顔が消えない。
……仕方がない。これでよかったんだ。何度頭の中で繰り返したかわからない言葉を、もう一度自分に言い聞かせた。
「はー、つかれた」
店先から声が聞こえて、机に突っ伏していた俺は体を起こして姿勢を正す。お袋だった。客ではないとわかり、俺は姿勢を崩し、頬杖をつく。
「ただいまー」
お袋は買い物袋――花柄のエコバッグを店先のボックスの中に降ろす。お袋は財布以外は持たずに出て行ったと思ったが、あんなバッグ持っていただろうか、と俺はぼんやり考えていた。
「なーに、辛気臭い顔して。せっかく休んだんだからもう少し明るい顔しなさいよ」
お袋は俺のほうへと歩いてくる。
「……たまに帰った実家でくらい気を抜いてたっていいだろ、ほっといてくれよ」
俺は言ったが、お袋は俺の顔を覗き込む。
「あんた、なんか悩みでもあるんじゃないの?」
「……ほっといてくれ」
同じ言葉を繰り返して、否定はしていなかった自分に気づく。
「隠したって判るのよ? あんたの母親なんだから。それでね? いいものがあるのよ。さっき駅前で、買い物袋がやぶけちゃってねー、困ってたところを通りすがった人に助けてもらったの。そのとき、一緒にこんなのもらったのよ」
「……は……?」
お袋が目のまえに差し出してきたものを見て、俺は間抜けな声を漏らした。自分の顔が頬杖から零れかける。
「は……はは……」
俺の口から笑いが漏れた。
まさか、こんなことがあるなんて、いったい誰が想像するだろうか?
「ほらこれ、悩みを解決してくれるお人形なんですって」
お袋は得意げに言う。
俺の目のまえに差し出されたものは、曇ったような銀色の先割れスプーン。
スプーンの先と柄の間の部分に、てるてる坊主のように端のほつれたハンカチが巻かれ、ハンカチが外れないよう、細い紐で縛って固定してある。
「名前も聞いたんだけど……なんていったかしら……そう、タイの……ワラ人形?」
「……さいきっく・わらしべ人形……」
俺の声は震えた。
「そう、たしかそんな名前ね!」お袋は空いている方の手のひらで腰を打つ。「あんた知ってるの? 都会で流行ってるのかしら。困ってる人の悩みが解決したら、つぎの誰かに渡すんですって。あたしの悩みは解決したから、それ、あんたにあげるわ」
差し出された人形を、俺は受け取る。手が震えた。
間違いなかった。
スプーンの先に油性ペンで書かれた顔はほとんど剥げ落ち、結んでいた紐は別のものに代わっている。
だけれどそれは間違いなく、あの日、ショッピングモールで茜と堀裕子、それと迷子の子供が一緒に念を送り、迷子の子供の手に渡った、裕子のスプーンで作られた人形だった。
「ははははは……」
俺は人形を握り締めて、もう片方の手で腹を抱えて笑い続けた。
ここまでくれば、誰も追いかけて来れないだろうと思っていた。距離を離せば、嫌でも縁は切れてしまうだろうと。
それがどうだ。縁は切れないどころか、こんなところまで追いかけてきた。
時に信じられないような奇跡だって起こしてみせる。それが、アイドル。
「はー……」ひとしきり笑い終えて、俺は立ち上がる。「ありがとう、お袋」
ありがとう、茜。裕子。迷子の子ども。そして人形をここまで継ぎ続けた、心優しき人達。
「俺さ、帰るわ」
「……え、今からかい?」
お袋は目を丸くする。俺は頷いた。
「ああ、親父によろしく」俺は居間に戻り、自分の荷物が入ったリュックサックのジッパーを開くと、乱暴に放り込んでいたスーツを引っ張り出す。「大事な仕事が、あるんだ」
「……そう」お袋は、俺の背に穏やかに声をかける。「がんばんなさいよ」
しわくちゃのスーツを着て、さいきっく・わらしべ人形を片手に握りしめたまま、俺は実家からバス停に向かって走りだす。新幹線の終発には間に合わないだろうが、今からならターミナル駅までは行けるはずだ。今夜はそこで一泊して、翌朝の新幹線で戻ればいい。
春菜の言葉を思い出す。
――がんばります。眼鏡に恥じないために。いつか、眼鏡のフレームとレンズの向こうに、ファンのみなさんでいっぱいの、きらきらした、私の……私だけの景色を見ることができるように――
俺は強く地面を蹴った。春菜だけの景色を、見せてやらなきゃいけない。
比奈の言葉を思い出す。
――ま、そんなに心配はしてないんスけどね。プロデューサーはたぶん、そこまで無責任にも悪人にもなれないヒトっスから――
俺は腕を振った。比奈には、最初からすべて見抜かれていた。
裕美の言葉を思い出す。
――私が私に自信を持てないだけだったんだ。いまは、ぜんぜん違って見える。前を向くだけで、こんなに世界って、きらきらして見えるようになるんだね――
俺はもっとスピードが出るように、上体をもっと前へと傾ける。
俺の世界は、裕美たちのおかげで輝いて見えるようになったんだ。
ほたるの言葉を思い出す。
――いつかきっと、この幸せをみんなにも届けられるように、頑張ります。お返ししなくちゃ……勇気、幸せ、想い出、たくさん、大切なものをもらったから――
俺は走る。
俺も、たくさん大切なものをもらっている。ほたるの出した勇気に足るものを、俺はまだ返しきれてない。
茜の言葉を思い出す。
――ライブ! すごく熱くて! すごく楽しかったです! ぜんぶ、私をスカウトしてくれたプロデューサーのおかげです、ありがとうございました!――
俺は走り続ける。
まだここからだ。もっと、もっと熱くなってもらう。もっと高いところへ行ってもらう。
世界が全部繋がっているように思えた。
早く帰ろう。俺は、あいつらのプロデューサーなんだから。
翌日午前。俺はプロデューサールームの扉を勢いよく開けた。
朝早くだというのに、プロデューサールームには先輩と、比奈、春菜、裕美、ほたるが揃っている。茜だけがその場に居なかった。
「おはようございます! 不在にしてすみませんでした!」
俺が挨拶をすると、全員が目を丸くした。
「プロデューサー!? どうしたんですか!?」
「すまない、いろいろ説明しなきゃいけないのはわかってる。……けど、ちょっと待ってくれ」
駆け寄ってきた春菜を、俺は片手を出して制した。先に、一番大事なことの筋を通しておきたかった。
「先輩!」俺は先輩プロデューサーの前に立つ。「すいませんでした!」
「あー、いいからさ、顔あげて」
先輩は頭を下げた俺に軽い口調で言った。
「比奈さんから大体の事情はきいたよ。親御さんの容態は、心配しなくていいんだよね?」
「はい」
「そっか、良かった」
先輩は穏やかに微笑む。このやりとりを聞いている春菜、裕美、ほたるが顔に疑問を浮かべていないところを見ると、俺が親の介護と言って実家に帰ったのは先輩にユニットのプロデュースを引き継いでもらうための嘘だということを、比奈からすでに知らされているのだろう。
「先輩」
俺は先輩の目を見つめる。先輩は射貫くような目で俺を見つめ返した。俺の心の底がひるんだ。だけど、もう小細工はしない。
しないと決めた。
「このユニットのプロデューサー……俺に、最後まで続けさせてください。もともと先輩が企画したユニットだし、先輩みたいにはできないかもしれない、けど……俺は、こいつらのプロデューサーをやりたい。絶対、こいつらを最高のユニットにします!」
俺は一礼して、ふたたび先輩を見据える。
先輩はしばらくのあいだ、俺のことを見定めるかのように、真剣な眼で見ていた。
それから、ふっと表情を崩して、俺のほうへ近づく。すれちがうようにして、先輩は右手で俺の右肩をぽんと叩いた。
「あたりまえだろ? ボクは病気で抜けた身なんだから、そもそもボクがどうこう言える立場じゃない。お前がここまで育てたユニットだよ。最後まで面倒を見るんだ」
「はい!」
「残してくれてた記録や資料を読んだ。それから比奈さんたちユニットメンバーからもきいたよ。立派な仕事っぷりだ。ほんとによくやってくれていたと思う。ボクの企画したユニット、プロデュースは、お前に任せる。よろしく頼んだよ。……『プロデューサー』」
「はいっ!」
二度目の返事は、声が上ずった。
「ま、ちょうどそのお願いを、ユニットのみんなからも聞いてたところなんだけどねー」
先輩は比奈たちを見渡す。
比奈は少し恥ずかしそうに笑い、春菜、裕美、ほたるはほっとしたような顔をしていた。
「彼女たちに言われたんだ。ユニットのプロデュースは、引き続きいままでのプロデューサーにやってもらいたいってね。そのとき、お前がボクにプロデュースを引き継がせて辞めるつもりだっていう話も、比奈さんから聞いたんだ」
「みんな……」俺は比奈たちのほうに向きなおる。「心配かけてすまなかった」
「おかえりなさい」
ほたるが目じりに涙を光らせて言う。
「心配したんだからね。でも帰ってきてくれてよかった」
裕美が微笑んだ。
「アタシの目に狂いはなかったってことにしとくっスよ」
比奈がやれやれといった顔で言った。
「生みの親より育ての親。これだけユニットのメンバーに慕われてるんじゃ、ボクの出る幕なんて最初っからなかったって感じだよね」
先輩は悪戯っぽい目と口調で言った。
「そうすると、あとは……」春菜は言いながら比奈と目を合わせて、頷き合う。「茜ちゃんのこと、ですよね」
「茜? ……なにかあったのか?」
俺が尋ねると、その場にいた全員が真剣な表情になった。
先輩が手を挙げて、話し始める。
「発端はボクだね。ボクがユニットのプロデュースを引き継ぐにあたって、最初にメンバーのみんなに連絡をしたときに、茜さんへの連絡が漏れていたんだ。記録を見て、ユニットに茜さんが加わっていたことを知って連絡先を探したけど、茜さんは美城のデータベースに登録されていなくて、見つけることができなかった。あとから、アルバイトとして登録されてたから、データベースでは検索できないことがわかったんだけどね。そもそも、なんでアルバイトで登録したの?」
「あ、そうか……」
俺は茜をアルバイトで登録していたことを思い出す。あのときは、先輩が帰ってきたときに正式登録するかどうか決めればいいと思っていた。先輩の復帰が遅くなったことで、すっかり頭から抜け落ちてしまっていた。
先輩は続ける。
「結局顔合わせの日まで茜さんには連絡をすることができなかったんだ。それでもユニットメンバーが顔合わせの日程を伝えてくれたみたいだから、そのときに挨拶をすればいいと思っていたんだけど……この部屋で茜さんがデータベースに登録されていない、という話をしているところを、部屋の外にいた茜さんに聞かれてしまったみたいでさ。それで、茜さんは自分がユニットから外されたと誤解して、居なくなってしまったみたいなんだよね」
「居なく……? 連絡はとれていないんですか?」
俺が言うと、比奈たちユニットメンバーはみんな首を横に振った。
「茜ちゃんのアルバイト証がこの部屋の前の廊下に落ちてたっス。それからみんなで連絡を取ろうとしたんスけど、ケータイの電源も切っちゃってるらしくて、どうしたものか……」
「……なるほどな」
俺は後ろ頭を掻いた。
「プロデューサー、どうしましょう」
春菜に聞かれて、俺はしばらく考え、頷く。
「戻って早々で悪いが、ちょっと出かけてくる」
「へっ?」比奈が間の抜けた声をあげた。「どこ行くんすか?」
「決まってるだろ、茜を探してくる」
「茜ちゃんを……って、ちょっと、プロデューサー!?」
俺は戸惑う表情の先輩と四人を尻目に、プロデューサールームを後にした。
プロダクションを出た俺は、さっそく茜の電話番号に発信してみた。応答はない。
二度目のコールも留守電への接続になってしまい、俺は電話での接触を諦める。
プロダクションの前で暫く考えたあと、俺は街中を河川敷へと向かうことにした。
茜が河川敷に来る、ということに、確信があったわけではなかった。
しかし、茜は家に閉じこもって冷静に考えるようなタイプではない。それなら、きっと普段の生活で使う場所を探すのがいい。今日は休日だから、学校に行くとは思えない。それなら走り込みのコースになっている、あの河川敷で待つのがいいだろう。
俺が走った河川敷へ向かう道は、まだ未熟だった数か月前の俺が辿った道だった。急にプロデューサーをやることになって、やる気なく形だけのスカウトを行っていたあの頃の。
もしも――もしも、あのとき茜に出会わなかったら、きっと今も俺は、あの頃のまま、適当に仕事をしていただろう。
それはそれで楽な人生なんだろうが、もうその頃に戻りたいという気はしなかった。
プロデュースすることの愉しみを、知ってしまったから。
河川敷に到着した俺は、記憶をたどり、以前にも通った芝生をのぼって土手の上の遊歩道に立つ。
午前の涼しい時間。散歩する人々や、自転車に乗る子ども、眼下に見えるグラウンドではサッカーの試合が行われている。俺の不安な心中とは裏腹に、さわやかな光景だった。
俺は遊歩道の遠くを見て――俺の心臓が大きくひとつ鳴った。土手の向こうから、近づいてくる人物。真っ赤なポロシャツを着ている。
ツイている。これも、いまも胸元のポケットに入っているさいきっく・わらしべ人形のご利益だろうか? 堀裕子。ひょっとすると、本物のエスパーなのかもしれない。
走ってくる赤いポロシャツの少女――茜は、俺の姿を認めると、そこで急激にスピードを落とし、クールダウンのためか、ゆっくりと歩いてこちらに近づいてきた。
「茜!」
俺は茜に向かって手を振る。
しかし、茜は俺から十五メートルほどの距離をあけて、止まった。
「茜……?」
俺の姿を見て、茜は辛そうに笑って、目を細める。
「プロデューサー……かえって、きてくれたんですね」
「ああ!」俺は茜の表情と開いた距離を疑問に思いながらも声をかける。「茜、みんな心配してるぞ、美城プロダクションに戻ってこい!」
俺の呼びかけに、茜はぎゅっと目をつぶって、両手を降ろしたまま握り締めて、首を横に振った。
俺は茜のほうに一歩、歩み寄る。
「……茜? どうしたんだ、ユニットのことなら」
「来ないでください!」
遮るように茜に言われて、俺は立ちどまった。
茜は両手で顔を覆って、また首を横に振る。
「私、行けないです! ……行けません!」
茜は悲痛な声をあげた。泣いているみたいだった。
俺はその場に立ちすくんだ。俺と茜のあいだの十五メートルが、やけに遠く感じられた。
ジョギング中の若い男性が、怪訝そうな顔をして俺たちの横を走り抜けていく。
「茜」穏やかな声になるよう努めて、俺は言う。「茜はユニットから外れたりはしない。茜が美城のデータベースに登録されていないのは、俺の連絡ミスだったんだよ。だから、茜が気にする事じゃない。正式な登録のし直しをする。だから、みんなのところに戻ろう」
茜は黙って俺の話を聞き、やがてゆっくりと顔を覆っていた両手を降ろした。
茜は涙でくしゃくしゃになった顔で、しかしやはり首を横に振る。
「違うんです、プロデューサー。私、逃げちゃったんです。みんな私のことも心配してくれてたのに、私が弱くて、みんなのことを信じきれなくて、それでみんなの前から逃げちゃったんですよ」
茜は力なく微笑む。右の頬を、涙が流れていった。
「怖かったんです。私は……私には、元気なことくらいしかとりえがありません。だから、私がアイドルじゃなくなったって聞いたとき、私、みんなといっしょに居る資格がなくなっちゃったって思っちゃったんです。みんな、強くて、かっこよくて、きれいで、キラキラしてて……私は、アイドルじゃなくなったら、みんなと並んで立てないんじゃないかって。それで、怖くて」
「そんなことは……」
「そんなこと、皆は気にしたりしないって、私もわかってます。でも、元気が取り柄で、何でも素直に信じて、バカ正直に突っ走る私が、私がみんなのことを信じられなくて、それで怖がって逃げちゃうなんて、そんなこと絶対にしちゃいけなかったんです! アイドルじゃなくなって、元気もまっすぐさもなくなっちゃったら……私には……みんなに合わせる顔がないんです……」
茜の声の最後のほうは、ほとんど掻き消えるように弱々しくなった。
俺は立ち尽くして、茜を見つめた。
ようやく、事態を理解できた。茜はユニットから外されたことをショックに思っているのではない。自分と戦っているんだ。アイドルであることが危ぶまれたときに自分がしてしまった行動と、これまで保ってきた自分とのギャップに苦しんでいる。
アイドルという称号も、仲間も『日野茜』が獲てきたものだ。しかし『日野茜』が『日野茜』でなくなってしまったら、そもそもの前提が崩れる。
どんなアイドルでも、いやアイドルでなくても、誰にでも起こりうる、自分自身と向き合う、嫌でも向き合わされる機会。
これはピンチでもあり、チャンスでもある。もし乗り越えれば、茜はさらに大きく、強い輝きを持てるだろう。
でももし、くじけてしまったら、自分が自分であることをやめてしまったら、そこで途絶えてしまう。
俺の幼なじみが、そうなってしまったように。
俺は目を細めた。こんなとき先輩ならどうするか――と、一瞬考えて、俺はすぐにその考えを頭の外に追い出した。
俺は俺のやり方で、茜をサポートする。もう、なにもしないで、大切な人が喪われるのは嫌だ。
俺はひとつ深呼吸をして、背中に土手の下り坂を背負うかたちで、遊歩道の端に立つ。
「茜」
俺が声をかけると、茜がこちらを見た。
「俺にタックルしてこい」
「……えっ?」脈絡のないことを言われて、茜は困惑した表情になる。「で、でも」
「ここがどこだか、覚えてるか?」
俺は茜に微笑みかける。
茜はあたりを見回して――泣きそうな顔で頷いた。
そう、ここは俺が初めて茜と出会い、そして茜をスカウトした場所。
アイドルとしての茜が始まった場所だ。
そして、プロデューサーとしての俺が始まった場所でもある。
「あの時のことを、思い出したいんだ」
「で、でも! 危ないですよ!」
「大丈夫、受け身はちゃんと取る」
「……」
茜は迷ったような顔をする。俺はもう一押しすることにした。
「頼むよ」
「……わかりました」
「全力で来いよ」
「はーッ、はーッ、はーーーーー……」
茜は深く、深く息をつく。俺は直立して茜を待った。
茜は目を閉じ、祈るように天を仰ぐ。そして――
「……ボンバーーーーッ!」
茜は空に向かって叫ぶ。
この声だ。鼓膜を破られそうなほど、強くて大きくて元気な声。あのときより、さらに声量が大きくなったんじゃないだろうか。レッスンの成果だと、俺はうれしくなった。
直後、茜は俺とのあいだ、約十五メートルの距離を疾走し、その全体重をかけて俺にタックルした。
衝撃。
小柄で体重の軽い茜とはいえ、人一人が全力でぶつかってくれば、衝撃は相当なものだ。重心を落として身構えることすらしていなかった俺は、そのまま斜め後ろ方向へとバランスを崩す。
俺は土手をごろごろと転げ落ちた。視界の上下左右が激しく入れ替わって、地面に身体のいろんなところをぶつける。もちろん、頭は両腕でガードしている。二度目なら慣れたものだ。
転がっているあいだ、たくさんの想い出がフラッシュバックする。茜との出会い、比奈との出会い、春菜、裕美、ほたるとのたくさんの想い出。
どれも、愛おしいものばかりだ。
土手の下で体はとまり、俺は河川敷の芝生に両手を投げ出して、大の字に寝転がった。
「プロデューサー! 大丈夫でしたか!?」
声のする方を仰ぎ見る。あの日は夕日で逆光だった。今は昼前、太陽が反対側の位置だ。茜の顔がよく見える。
「はー……ああ、大丈夫だ。ケガもしてない」
「スーツ、汚れませんでしたか!」
茜は土手を降りて、俺のところまで走ってくると、膝をついて、寝転がる俺の顔を覗き込んだ。
「ああ、濡れてもいない。それに、どうせこの前適当にスーツケースにしまってシワだらけだし、そろそろ――」
そこまで言うと、茜ははっとした顔をした。
「……クリーニングに出そうと思っていた、ですか?」
「ああ、その通りだ。……ははっ」
俺は笑う。それでようやく、茜も微笑んだ。
「懐かしいですね」
「俺もそう思う。でも、たった数か月前のことなんだよ。すごくいろんなことがあったな。茜がアイドルになって、皆でいろんな仕事して……濃かったよな、この数か月」
「はい」
「……楽しかった」
「……はい」
茜は穏やかに肯定する。
「……茜たちに、言ってなかったことがあるんだ」俺は茜を見た。茜は不思議そうにしている。「俺、茜たちのプロデューサーやるって言っといて、ずっと自分から逃げてたんだよ。幼なじみとの小さいころの約束が果たせなくてさ。幼なじみとはもう会えなくなって、それがトラウマになった。ずっと適当に、自分から逃げたまま生きてた。お前たちのプロデュースも、最後に先輩に任せて逃げようとしてたんだ。怖かったんだよな、昔に俺自身がした喪失を繰り返すのが」
「そんな、プロデューサーは私たちをすごくサポートしてくれています!」
「そう思うか? でも実際は、実家に逃げ帰って、結果、茜にも辛い思いさせてさ。茜はみんなに合わせる顔がないって言ってたけど、俺のほうがずっとダメだったんだよ。みんなに本当の顔を見せずに仕事してたんだからな。でも……実家に引きこもってたら、こいつに、再会した」
俺は胸のポケットから、さいきっく・わらしべ人形を取り出す。茜があっと驚きの声をあげた。
「これ、ユッコちゃんの!」
「信じられないよな。お袋がもらってきた。そのとき思ったんだよ。最後までお前たちのプロデュースをしたいって。実家に帰って、こんな奇跡に出会うまでそんな自分の気持ちにすら向き合えなかったんだからな。笑えるよ、自分の弱さに」
俺は茜にさいきっく・わらしべ人形を握らせる。
「俺もみんなにも、茜にも合わせる顔はないけど、頑張るよ。失敗した分はこれから取り返す。茜はどうだ、アイドル、続けたいか?」
「私……」
茜はさいきっく・わらしべ人形を握り締めて、涙を流した。
熱い雫が俺の顔にかかる。
茜はふうう、と震えた熱い息を吐いて、それから目を見開く。
「私、アイドル、やりたいです! みんなといっしょに! 沢山迷惑をかけてしまいました! でも、やっぱりみんなと一緒にやりたいんです、こんどこそ、元気な私で、最後まで!」
俺は目を閉じて、茜の言葉を心に刻んだ。
「ああ。それで十分だと思う」俺は体を起こして、茜の前に立つ。「みんなに申し訳ないと思った分は、二人ともこれから挽回しようぜ。辞めるのはいつでもできる。でも、辞めてしまったら、取り戻したいものも二度と取り戻せないんだ」
言って、俺はポケットから名刺入れを取り出し、茜に名刺を差し出す。
「日野茜さん。貴女を、スカウトします。アイドル、やりましょう」
俺が差し出した名刺を、茜は目に涙を溜めて、けれども、晴れやかな笑顔で受け取った。
「はいっ!」
河川敷に、茜の大きな声が響いた。
・・・END
「一体何がどーなったら、そんなボロボロになれるんスか」
茜を連れてプロデューサールームに戻った俺を見て、比奈が呆れたような声で言った。
たしかに、もともとしわくちゃだったスーツで土手を転がったものだから、枯草がまとわりついて、俺は事故にでもあったかのような悲惨な姿になっている。
「でも、茜ちゃんが帰ってきてくれて、よかったです!」
春菜が嬉しそうに言うと、裕美、ほたるも大きく頷いた。
「へへへ……ご迷惑とご心配をおかけしました」
茜は恥ずかしそうに頭を掻くと、丁寧に礼をした。裕美とほたるが駆け寄り、茜に抱き着く。
「ま、一件落着、かな? あとは新曲のリリースだね。みんな、頑張って。応援してるよ」
先輩が穏やかな顔で微笑んだ。
「はいっ!」
俺たち六人は、そろって大きな声で返事をする。