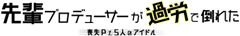
控室の中。テーブルに座ったほたるはじっと、原稿を読み続けている。丁寧に、何度も、何度も。唇が小さく動いていた。ときおり、原稿から視線を外して、不安そうな顔をして息をつき、また原稿の確認に戻る。
俺はそれを、ほたるの対角に位置する席に座って見ていた。
待合室の中では、アナログの時計の針の音だけが響いている。
今日はほたる単独の仕事だった。都内の繁華街で開催されているジャズフェスティバルのナレーションの仕事だ。
ジャズフェスティバルでは街中の飲食店や公園、商業施設などの様々な場所をステージとして、同時多発的にジャズライブが開催される。ほたるがナレーションを担当するのは、商業施設屋上にあるビアガーデンに設置されたステージで、それなりのキャパシティを持ってはいるが、それでも多くのステージのうちのひとつにすぎない。
すなわち、緊張するような仕事ではない。個人名やバンド名を間違えないようにするのは当然だが、紛らわしい名称や、気を遣うような難しい出演者もいない。
「ほたる」
俺が声をかけると、ほたるは顔をあげて、俺のほうを見た。
顔が暗い。唇をきゅっと結んで、不安そうにしている。
「ステージ、見てみないか。ナレーションはテントからで、客からも死角になるそうだが、実際に見たほうがイメージできて、不安がまぎれるかもしれないぞ」
「……そうですね、そうしてみます。ごめんなさい……」
「いや……」
謝る必要はないと言おうとして、俺はその言葉を飲みこむ。きっと、ほたるはそういう言葉が欲しいわけではないと思った。
最上階に設置されている控室を出て、階段を上り屋上へ。まだ開店前、飲食をする客のいないビアガーデンは椅子とテーブルだけが並んでいて、物寂しい雰囲気だった。
正面にステージが見える。ステージ横には大型のイベント用テントが張られていて、舞台袖とナレーション用の席を兼ねているようだ。
「行ってみよう」
ほたるとともにテントの中へ。パイプ椅子と長机がいくつか置かれており、長机のうちのひとつに音響設備がセッティングされている。
スタンドマイクが置かれた座席があった。ここにほたるが座ることになるのだろう。
「座ってみるか?」
ほたるに促してみるが、ほたるは首を横に振る。
「……機材を壊してしまうと、迷惑がかかりますから……」
俺は肩をすくめた。
「そうか。大丈夫だとは思うけどな……ほたる、根を詰めすぎて固くなるのもよくない。フェスティバルだしな。天気もいいし、すこし風に当たってから戻ったらどうだ」
「そうですね……」
ほたるはほんの少しだけ弱々しい笑顔を見せて、屋上ビアガーデンの中央へ歩いて行く。それから不安そうな顔で空を見上げた。
「……なかなか症状が重いな……」
ほたるに聴こえないように、俺はつぶやいた。
ユニットをプロデュースするにあたって、すでにプロダクションに所属しているアイドルについては事前にできるだけのことを調べた。ほたるについて得られたのは、白菊ほたるというアイドルは、自分に運がないと思っている、ということだった。
美城プロダクションより前にほたるが所属していた事務所は殆どが倒産しており、過去出演したイベントには天候、事故などの原因で中止、内容の変更が散見される。
ほたるは、それを自分の不運のせいだと考えている。
これは非常に根の深い話だ。なぜなら、実際にほたるが不運の持ち主であるかどうかということは実証不可能だからだ。そんなものは評価によってどうにでも考えることができる。ちなみに俺はここまで数か月ほたるに接していて、ほたるが原因でなにかの不利益を被ったとは考えていない。
一方で、運、という言葉にほかの業界よりも重きがおかれるのもまた芸能界だ。なにがヒットするかの予想が困難な芸能界においては、運も実力のうち、という言葉が非常によく流通する。
「少し風が強いですね」
ほたるが自分の髪を押さえて言う。陽光に照らされ、誰もいない屋上にぽつんとたたずむロングスカート姿のほたるは非常に絵になっているのだが、どうにもイメージがネガティブだ。まるで荒廃した世界にひとりぼっちで残されているみたいに見える。
ほたるにはきちんと実力がある。自分自身の気持ちに折り合いがつけば、化けることができるはずだ。
だが、それをさせるには、ほたる自身が作ってしまっている壁が厚すぎる。
「天気は大丈夫でしょうか」
「大丈夫だろう、降水確率は気にするようなものじゃなかったし、台風予報も確認したが、コースはかなり離れていたからな」
「そうですか……」
ほたるはそれでも、不安そうに空を見た。
「よし、確認はこんなものか。ほたるはほかに見たいところはあるか?」
「いえ、大丈夫です」
「じゃあ……とりあえず、控室に戻るか……っと」
俺がそう言ったとき、スーツのポケットの中でスマートフォンが鳴りだした。俺は画面の表示を見る。茜の番号だった。
「応援に来ましたっ!」
茜、比奈、春菜、裕美の四人が控室に入ってくる。開演時間まであと三十分程度。茜たちはオフの日なので、単純にほたるを激励したあとにイベントを楽しむつもりだろう。
「……どうした?」
俺は思わず四人に尋ねる。入ってきた茜の顔は見るからに不機嫌そうで、春菜、裕美もどこかぎこちない表情をしている。比奈に目線を送ると、苦笑いを返された。
「なんでもありませんっ!」
茜は言うが、顔は笑ってない。よくも悪くも嘘をつけないのが茜だ。
「……私、ですか?」
ほたるはぽつりと言う。
「あっ! いやっ、その、ええと、ほたるちゃんは、そのっ!」
茜が明らかに動揺したので、ほたるは申し訳なさそうに目を伏せる。茜の後ろで比奈たちがそれぞれに「あちゃあ」といった顔をした。
繰り返すが、よくも悪くも嘘をつけないのが茜だ。
「なにがあった?」
俺は尋ねる。隠せないなら問題の中身をきいたほうがいい。
「……ここに来るまでに、ほたるちゃんがナレーションとして出演していることを不安に思っているって話がきこえてきたっス」
比奈はほたるのほうを気遣うように見て言った。
「なるほどな」俺は隣にいるほたるの背を軽く叩く。「気にするな」
「大丈夫です、いつものことですから。……すいません」
「ほたるちゃんっ!」
茜が半ば叫ぶように言った。そのくらい、ほたるの表情は色を失っていた。
「大丈夫ですよ」
ほたるは微笑む。微笑むけれど、力はなくて、本当に何もかもが空っぽで、どうしようもなく、どうにもできない微笑みだった。
俺も喉が詰まるような気持ちになった。いったい、なにがあったら、こんな表情をするようになってしまうのか。
茜が低くうめく。
「……みんな、とりあえず座ってくれ」
俺は控室の椅子をすすめる。四脚しかないので、茜と俺以外の四人が用意された椅子についた。
重たい沈黙が流れる。
俺はひとつ息をついた。
ほたるが作っている壁は厚い。それでも、ほたるはまだ折れていない。だからこそ、アイドルでいようとし続けている。
それなら、まだどこかに突破口があるはずだ。
やがて、ほたるが口を開いた。
「ほんとうに、いつものことなんです。私、不幸にみまわれることが多くて、これまでも所属事務所が倒産したり、身の回りのひとが事故にあったり、病気になったり……イベントも、なにかトラブルがあったり、皆さんに迷惑をかけてしまって……」
「私たちには、特にそういうことはないみたいですけど……」
春菜が言う。ほかの三人も頷いた。
けれど、ほたるは首を振る。
「皆さんが私とこのまま一緒に活動していれば、悪いことが起こるかもしれない……ううん、きっと起こります」
春菜は小さく唸って、口をつぐんだ。
「そんなことばっかりだから、出演者やスタッフさんが私が居ると不安になるのも、しょうがないんです。私が不幸だから……ごめんなさい」
話を聞いていた裕美が眉間にしわを寄せた。
「思い込みとかじゃないのかな」
裕美が尋ねる。ほたるは応えない。
「アタシも思い込みだと思うっスよ、アタシなんて一回落選してからの拾い上げでここにいるんスから、むしろほたるちゃんと一緒にアイドルできて、ラッキーってことにならないスかね?」
「それは、比奈さん自身の力ですよ、私なんかじゃ、とても」
と、ほたるが言ったときだった。
時計の音以外は無音の控室にタ、タ、と何かを叩くような音が聞こえて、俺たちは音のしたほうをみる。
窓に、水滴のあと。
「雨……?」
俺は窓から空を見る。さっき屋上に上がったときとは正反対に、空にはぶ厚い暗い雲が立ち込めていた。風は先ほどよりも強くなり、すぐに大粒の雨が窓を打ち始める。
「天気予報では雨の心配なんてないって言ってたのに……」
裕美が立ち上がり、窓のところまで歩いてくる。
俺はスマートフォンで天気予報を確認する。勢力を増した台風が急激に進路を変えたと速報があり、都内が暴風圏内に入っていた。
「やっぱり……ごめんなさい……」
ほたるはそう言って、座ったままで頭を下げた。
四人は、なにも言わなかった。
俺はもうひとつ、溜息をついた。
ほたるの不幸を思い込みに過ぎないと説明することはできる。たとえば所属事務所が倒産したという話だが、中小企業なら五年で八十五パーセント近くが倒産する。ましてや芸能界は先の読めない業界だ。普段の生活であまり倒産の言葉に触れることはないかもしれないが、実際には次々に会社が生まれ、消えていく。俺が美城プロダクションに所属する前の事務所も、今はもうない。
問題なのは、ほたるに関わった人々がほたると不幸を結び付け、それをほたるが受け入れてしまっているという点だ。禍福は糾える縄の如しと言うが、ほたるに起こったことが幸運なのか、それとも不幸なのかはほたると周りの人々の評価次第だ。悪いことはもっと悪いことの回避の結果だと喜ぶことができるかもしれないし、同じように幸運を嘆くことだってできる。前の事務所が倒産していなければ、今の事務所に所属してはいなかっただろう。幸不幸は相対的な問題で、絶対的に評価できるものではない。
それでも人々は、そしてほたるは自分に起こったセンセーショナルなことだけをクローズアップしてほたる自身と結び続ける。
例えば、晴れ男の芸能人がいたとしよう。移動先が晴れであったり、移動したとたんにその場所の天候が崩れれば、人々は喜んでその情報を拡散する。けれども、それは確率論で語られることは決してない。晴れ男が出会った雨は無視される。そうやって、晴れのエピソードだけが積み重なり、晴れ男は晴れ男として作られ続けていく。
それが本人をキャラクター付けるプラスの要素になら喜んで便乗すればいい。しかしほたるの場合はどうだろうか。
少なくとも、俺の目のまえに座るほたるはずっと、空っぽな顔をしている。
まずは場の空気を変えることが必要だと、俺は判断した。
「あー……茜、みんなの分のドリンクをなにか買ってきてくれないか」
俺は茜に千円札を渡す。
「わかりました!」
茜は控室の扉を開け、出ていこうとする――と。
「なんで急に降りだしてんだよ、意味わかんねぇな」
「あれだろ、ほら、不幸アイドルの……」
外の会話が部屋の中に聴こえてきた。
「おい、聴こえるぞ、ドアが……」
「やべ」
声は遠ざかっていく。
茜はドアの前に立ち尽くしていた。
間が悪すぎる。俺は思わず片手で顔を覆った。
まさか、本当にほたるの不幸が原因なのか――? と、一瞬疑い、すぐにその考えを頭から追い出した。
ほたるはずっと、机の上のなにもないところを見つめている。
「っと、すいませーん、出演者のかたと、プロデューサーさん……」
別の声が聞こえて、俺はドアのほうを見た。
茜がドアの前から離れる。開いたままのドアの前には会場の男性スタッフが立っていた。
「すいません、見てのとおりの天気で、ちょっと開演を見合わせています、どうなるかわからないですが、ひとまず待機していただいて……続報、またお伝えしますんで」
「わかりました」
俺が返事をすると、男性スタッフは去っていった。
茜が扉を閉める。
窓の外はまだ強い雨風が続いていた。
沈黙。
俺がもう一度茜にドリンクの買い出しを指示しようかと考えていたときだった。
ほたるが、ぽつり、と話し始める。
「わたし、大丈夫ですよ……すみません、ずっとこうなので、もう、慣れてしまいました」
ほたるはそういって笑顔を見せる。
「ほたるちゃん……」
春菜がかすれた声でつぶやいた。
「頑張っても、どうにもならないこともあります。……でも、アイドルは、やりたくて……でも」言いながら、ほたるは迷うように視線を泳がせる。「みなさんに、迷惑がかかってしまったら……私のせいで、ユニットに、なにか悪いことが起こったら……」
俺たちが黙っていると、茜がゆっくりと一歩、ほたるのほうに歩いた。
ほたるは、笑顔のままで、俺たちのほうを見て言う。
「やっぱり私、このユニットから、いな――」
「ほたるちゃんっ!」
ほたるの声を、茜の叫ぶような声がかき消した。
茜はほたるほうへずんずんと歩いて行く。
その途中で一度俺に向きなおり、さっき俺の渡した千円札を差し出してくる。
俺がそれを受け取ると、茜はほたるの横に立った。
「私は、ほたるちゃんと一緒にやりたいです!」
茜はまじめな顔で、きっぱりと言う。
「私も、ほたるちゃんとユニットやりたいですよ!」
春菜が続いた。比奈と裕美も大きく頷く。
ほたるは困ったように笑った。
「ありがとうございます、でも……こんなふうに」ほたるは窓の外を示す。「ステージ自体が、私のせいでだめになってしまうこともあるんです。私は、皆さんに羽ばたいてほしい」
「ほたるちゃんにも羽ばたいてほしいんだ」
裕美がすぐに切り返す。ほたるは少し、たじろいだ。
「そうですっ! ほたるちゃん、みんな同じ気持ちですよ!」
茜が笑顔になる。
「で、でも……」
ほたるは不安そうに俺と四人の顔を見渡して、それから視線を落とす。
まだ、壁が崩せないか。俺がそう思っていた矢先、茜がほたるの手を取った。
「やれますよ! 不幸になんて負けなけいくらい熱くなれば、ステージだってできます!」
茜はまっすぐほたるの目を見た。
ほたるは、きょとんとして茜を見ている。
「みんな! 行きましょう! ほたるちゃん、立ってください!」
茜はほたるの手を引く。
比奈、春菜、裕美は一瞬戸惑った顔を見せたが、すぐにお互い頷き合うと、立ち上がった。
「え、皆さん、なにを……?」
戸惑うほたるを連れて、五人は部屋を出る。
俺はそのあとを追いかけようとして……その前に、スマートフォンを操作して電話をかける。先ほど打ち合わせをした男性スタッフだ。数回のコールで応答があった。
「あ、すいません、美城プロダクションの……ええ、そうです、ええ。すいません、急遽出演者用の服を調達していただきたくて……費用はこちらで出します、確か、下のフロアにショップがあったと思って……はい、それでサイズは……」
一分ほどで電話を終えて、俺はほたるたちを追った。
屋上へ向かう階段の前に、ほたるは立っていた。
階段の途中には茜が立って、ほたるに向かって手を差し伸べている。
ほたるは追いついた俺のほうを見る。
ほたるは迷っているようだった。
右手は握り締めて、胸の前に。
左手は不安そうにスカートの裾を掴んでいる。
「プロデューサーさん、私……」
「ほたる、茜たちと向き合ってみてくれ」
ほたるは小さく口を開閉させて、それからゆっくりと茜のほうへ向き直る。
俺はその後ろに立った。
「ほたるちゃん!」茜は微笑む。「ほたるちゃんは不幸なんかじゃありません! もし不幸なら、不幸ごとキラキラすればいいんです! 私たちだって一緒ですから! 行きましょう!」
俺はほたるの背をそっと押す。
ほたるは迷うような足取りで、それでも少しずつ、茜のほうへ歩いていく。
階段をのぼり、ほたるは差し出された茜の手を、おずおずとにぎった。
茜はそれをぎゅっと握ると、強くひとつ頷いて、ほたるを引いた。
ほたるは茜に引かれて、茜と一緒に階段を上る。
「私はほたるちゃんと一緒に居て、困ったことなんてありません! ううん、楽しいことばっかりでした! だから、ほたるちゃんも私たちと一緒に居たいと思ってくれたら、嬉しいです!」
茜はほんのすこし頬を染めて、ほたるに言う。
「……ありがとう、ございます」
ほたるは恥ずかしそうに笑った。
階段を上ると、その途中には春菜が立っていて、茜のときと同じように、ほたるに手を差し出している。
「ほたるちゃん」春菜は言いながら、もう片方の手で眼鏡のテンプルをつまむ。「私も、自分に自信がなくて、怖かったときがありました。怖いっていう気持ちに身を預けるのって、簡単なんです。でも、それじゃだめなんだって、不安に立ち向かっていかなきゃって今は思えます。私を支えてくれる人達にも、眼鏡にも、失礼になってしまいますから。……そう教えてもらったんです。ほたるちゃんも、立ち向かってください。大丈夫です、私たちも一緒に、立ち向かいますから!」
茜はほたるとつないでいた手を離し、ほたるの背を軽く押す。
ほたるは階段をのぼり、春菜の手をとった。
二人は階段を上っていく。
「怖いと思ってるときって、怖いものが普段より大きく見えるみたいなんです。レンズのくもりが取れて、怖がらずに見られるようになったら、そんなに怖がらなくてもいいんだって思えるようになりましたよ。だから、きっとほたるちゃんも大丈夫です」
春菜は微笑む。
「もしも一人で不安なら、眼鏡どうぞ。私たちが、ほたるちゃんの眼鏡になりますから」
階段を上ると、踊り場には比奈が立っていて、ほたるに手を差し出している。
「春菜さん……」ほたるは春菜の顔を見て、それから比奈のほうを見る。「比奈さん」
「ほたるちゃん」比奈は穏やかに微笑む。「アタシはほたるちゃんがいないユニットなんて考えられないっス。そういうコンセプトだからとかじゃなくて、アタシは五人のうち誰が欠けても嫌っス。そんなところまできてしまったっス」
春菜はほたるとつないでいた手を離し、ほたるの背を軽く押す。
ほたるは階段をのぼり、踊り場に居る比奈の手をとった。
二人は階段を上っていく。
「物語の主人公には困難がつきもので、それを乗り越えてこそ輝くっス。アタシたちは五人でひとつのユニットなんスから、ちょっとの不幸くらいチームワークで乗り越えるっスよ。一蓮托生っス」
屋上へ向かう階段を上がると、その途中には裕美が立っていて、ほたるに手を差し出している。
「ああ……」
ほたるは裕美を見上げて、泣きそうな声をあげる。
比奈は頭を掻く。
「筋書きをくれる腕のいいプロデューサーもついてるッス。もっと気楽に、乗っかっていいと思うっスよ」
比奈はほたるとつないでいた手を離し、ほたるの背を軽く押す。
ほたるは階段をのぼる。
裕美はほたるの両肩に手を置き、ほたるを見つめ、それから背中に手を回して、優しく抱きしめた。しばらくそうしてから、裕美はほたるから身体を離して、ほたるの手をとった。
二人は階段をのぼっていく。
「ほたるちゃん、このまえのラジオのとき、手を握ってくれてありがとう。私、あのとき、ほんとうにうれしかったよ。だから、お返ししたいと思ってたんだ」
屋上の扉の前に二人は立つ。その後ろに俺たちが追い付いていた。
「つぎは、ほたるちゃんの番」
裕美は屋上ビアガーデンの扉を開ける。
扉の向こうは暴風雨だった。
椅子は風で飛ばないように片付けられ、固定されたテーブルだけが残っている。当然、人の姿はない。
「裕美ちゃん、やっぱり……」
ほたるは荒れ狂う空を見て言う。唇は震えている。しかし、裕美は首を横に振った。それから、睨むように空を見る。
「ほたるちゃん、ちょっとだけ、無茶かもしれない。でも、きっと今なんだよ。私たちがついてるから、あとはほたるちゃんが勇気を出して」
裕美はほたるから手を離し、一歩前に出る。強い雨と風が容赦なく裕美に襲い掛かった。
「裕美ちゃん」
心配そうに裕美を呼んだほたるの横を、茜、比奈、春菜が通り過ぎて、裕美と同じくほたるの前に出た。
「ほたるちゃん!」雨の中で茜が笑う。「勇気があれば、大丈夫です!」
「勇気……」
ほたるは小さくつぶやく。
それから、目をぎゅっと閉じ、肩をすぼめて、なにかをじっと考えているようだった。
茜たち四人は雨でずぶぬれになっている。
やがて、ほたるは目をあけると、そっと一歩、茜たちのほうに歩み出す。
「ほたるちゃん!」
春菜が嬉しそうに言った。
「さあ! ステージへ行きましょう!」
茜が言うと、春菜、茜、ほたる、裕美、比奈の順に横一列になり、手を繋いで行進するように、誰もいないビアガーデンを五人で闊歩していった。
恫喝するかのように、雷雲が轟音を響かせる。
それでも五人は止まらない。
五人はステージの上に立つ。
俺はそれを、ビアガーデンへと出る扉のところから見ていた。
ほたるを除く四人は、凛とした表情でステージから無人のビアガーデンを見据える。
ほたるだけが、まだ不安そうにしていた。
空は真っ黒い雲がぐねぐねとうごめいている。
強風が吹いて、横殴りの雨が五人を責めた。
「ほたるちゃん! 勇気をだしてください!」茜が叫ぶ。「五人で、一緒にやりましょう! 不幸なんて、みんなで吹き飛ばすんです!」
ほたるは悲痛な顔をしていた。頬を流れていく水滴は雨のようにも、涙のようにも見えた。
「大丈夫っスよ、ほたるちゃん。きっとアタシだって、ほたるちゃんに迷惑かけてることがあるし、これからもかけちゃうこと、あるっス。お互い様っスよ」
比奈が歯を見せて笑った。
「そう、だから!」春菜は眼鏡についた雨粒を拭うこともせず、叫ぶ。「ほたるちゃんの声を、聴かせてください!」
「ほたるちゃん、私のつぎは、ほたるちゃんの番だよ! 聴かせて、ほたるちゃんの声、ほたるちゃんの、ほんとうの気持ち!」
裕美が言う。
ほたるは、大きく息を吸って、吐き、目を閉じて頭を垂れる。
祈っているみたいだと、俺は思った。
そのまま、十秒ほど。
それから、ほたるが顔をあげた。
「おっ」
俺は声を出していた。
ほたるが、笑っていたように見えたからだ。
そのとき、風だけが一瞬止まった。
ほたるは目を開く。一瞬だけ視線を泳がせて、それでも決意を秘めた目をして、大きな声で空に向かって、空気を震わせて叫んだ。
「私、みなさんと一緒に、やりたいです! キラキラしたいです! やめたくない! 不幸でも、不幸かも、しれないですけど、それでも! みなさんといっしょにユニットをやりたい!」
ほたるは叫びきり、茜たち四人はぱっと顔を輝かせた。
その直後だった。
雨は急に弱まり、空から逃げ去るように流れて行った雲のあいだから、太陽がのぞく。
まぶしさに思わず目を細めたときには、雨は止んでいた。
「は……」
俺の口から間抜けな声が漏れた。
「すごいっ! すごいですよ! 奇跡です!」茜が大きな声で叫び、跳ねる。「ほたるちゃんが起こした、奇跡です!」
「はいっ! こんな、こんなことって!」
ほたるは信じられないといった顔をしている。
五人は抱き合って、笑い泣いていた。
「ははは……」
その光景を遠目に見ながら、つられて俺も笑う。
たしかに、奇跡のような光景だった。
もちろん、奇跡だって合理的な説明をつけることはできる。急激に進路を変え、加速した台風は、この会場近くをかすめて飛び去って行った。暴風雨は一時的なもので、もともと長く続くようなものではなかった。それだけの話ではある。
だけど、こういう奇跡は、奇跡として素直に受け取るべきってもんだろう。
ほたるが起こした、ほたるたちのための奇跡として。
「壁は崩れたか。雨降って地固まるってところかな」
俺は喜びあっている五人を見ながらつぶやいた。
ほたるの頬は、雨と涙とできらきら輝いていた。
「ほたる、そのままじゃ風邪ひくぞ。会場のスタッフに依頼して控室に着替えを用意してもらった。フェスティバルは押しで決行だそうだから、始まる前に着替えてくれ」
「はい、ありがとうございます」
雨の上がったビアガーデンで、ずぶ濡れのほたるは頭を下げる。さっきまでとは違って、どこかすっきりした顔をしていた。
「プロデューサー、アタシたちの分は……」
同じくずぶ濡れの比奈が尋ねるが、俺は笑って首を振る。
「ない。オフのお前たちにまで用意する理由がないだろ?」
「まぁ、そうっスけど」
比奈は不満げな顔をする。ちなみに、ほたるの分も予想外の出費なので、経理担当が首を縦に振らなければ俺の自腹になる可能性があるのだが、五人の前では口に出さないことにした。
「お前たちも風邪ひくとよくないからな。せっかく来たとこ残念ではあるが、体調管理はしっかりしろ。近くにいくつか銭湯がある。そこの入浴代くらいなら出してやるぞ」
「うーん、残念ですけど、プロデューサーの言う通りです。仕方ないですね。ほたるちゃんの最初の声だけ聴いていきましょうか」
春菜が言うと、茜、比奈、裕美が頷いた。
それからほどなくして、ジャズフェスティバルのビアガーデン会場公演は、当初より予定を遅らせて開催された。
「大変長らくお待たせいたしました。ジャズフェスティバル、ビアガーデン会場、公演開始いたします」
雨の上がった会場には、ほたるのアナウンスの声が響き渡る。
その声は明るく、迷いはもう見えない。
一組目のバンドの演奏が始まり、ほたるはマイクのスイッチを切る。それから、胸に手を当てて、ふぅ、と深く息をついた。
「緊張してるか?」
俺はほたるに尋ねる。
「はい。……不安なんです」ほたるは困ったように笑う。「こんなに幸せに思えることって、いままでなかったんです。楽しいって思ってもいいなんて、なんだかまだ慣れなくて。……アイドルになることを、あきらめないで、よかった」
ほたるは目を細めた。
「……そうだな」
俺も目を細める。ほたるは、あきらめなかったから、届いた。
「いつかきっと、この幸せを皆にも届けられるように、頑張ります。お返ししなくちゃ……勇気、幸せ、想い出、たくさん、大切なものをもらったから」
そう言って、ほたるは俺に笑いかけた。
ほたるはもう、大丈夫だろう。
・・・END
後日のプロデューサールーム。
俺は黙ってキーボードを打ち続ける。
デスクに置かれたフォトフレームは、茜たちの写真のスライドショーが流れている。
この写真も、だいぶ増えた。
俺は手を止め、フォトフレームを一瞥する。
そのとき、プロデューサールームの扉が開く。
入ってきたのは、見知った顔。いや、さすがに少し痩せたか。
「よっ」
久しぶりに聴いた、軽快な声。
俺は椅子から立ち上がり、笑顔を返す。
「おかえりなさい、先輩」