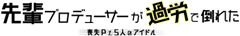
駅の改札を出ると、荒木比奈は自分の腕時計を確かめた。待ち合わせの時間にはまだすこし余裕がある。
比奈はあたりを眺めてみる。都心からそれなりの時間電車に揺られてきた初めての場所だったが、かなり拓けた街のようだ。駅もそこそこに大きく、改札の中にもいくらかの店舗が入っている。
駅舎からはペデストリアンデッキを通して、南北それぞれの商業施設にアクセスできるようになっている。デッキの下に見えるバスターミナルもかなりの規模だ。
「思ってたより大きな街だったんスね……」
比奈は誰へともなく言って、スマートフォンに地図を表示させてから、南側デッキのほうへと歩いていく。
デッキに立つと、穏やかな西日が目に飛び込み、比奈は目を細めた。帽子を深めに被りなおして、デッキの欄干に背を預け、比奈はスマートフォンで周辺の情報を確認していく。
「フムフム……北側は繁華街っスね……カラオケボックス、居酒屋……リア充向けって感じっス。アタシのいる南側は……、大学、ホール……むっ、この書店、かなりの大型っスね……場所は……」
比奈はスマートフォンから顔をあげて街を眺める。それから、目を見開いた。
「あっちのビル、アニメショップが入ってるっス……! それだけじゃない、レンタルと古本もあるっス!」
比奈は腕組をすると、満足気な顔をしてひとつ頷いた。
「すごく、いい街じゃないっスか……!」
力強く言ってから、比奈はふたたび時計を見る。
待ち合わせの時間に余裕があるとは言え、さすがにショッピングに興じるほどの時間はない。
比奈は後ろ髪引かれる思いを断ち切って、駅舎の中へと戻った。
待ち合わせ時間までは十分弱。
比奈は人から見つけられやすいところに立とうとして、プロデューサーから自分がアイドルとして活動していることを自覚するように言われたことを思い出し、目立たないように駅舎内の壁際に沿って立った。
「駆け出しっスし、オーラとかないんで、大丈夫だとは思うっスけど」
小さくつぶやいて、スマートフォンに視線を落とす。
画面はメッセージの着信を知らせていた。
送信者は安部菜々。メッセージには『いま、早苗さんがそちらに向かってます! そろそろ着く頃だと思いますよ!』と、ウサギの絵文字付きで書かれていた。
「おまたせー、比奈ちゃんよね?」
比奈が顔をあげると、そこにはキャップを被った片桐早苗が立っていた。
「あ、片桐早苗さん……スか?」
「そう! はじめまして!」
「はじめましてっス」
比奈はぺこりと頭を下げた。片桐早苗は同じ美城プロダクションのアイドルの一人だ。トランジスタグラマーなプロポーションに、頼りがいがあるが、はじけているときは一人でもとことんまで暴走するような、ギャップのあるキャラクターで人気がある。
今日は安部菜々の自宅で、オフまたは仕事上がりのアイドルを集めてパーティーが企画されていた。比奈と早苗はそこに招かれており、菜々の自宅を訪れたことがない比奈を、早苗が誘導することになっている。
「それじゃあ、挨拶はこのくらいにして、いきましょっか! せっかくのオフ、満喫しましょ!」
早苗は比奈の背中を軽く叩いて歩き出す。
「はいっス」比奈は早苗のあとについて歩く。「……それにしてもアタシ、ホームパーティーなんてリア充っぽいこと初めてで……出てから気づいたんスけど、こんなカッコでよかったのか……」
比奈はいつものジャージ姿で、両手を広げた。
「ホームパーティー!?」早苗は驚いたように言って、ぷっと吹きだす。「誰が言ってたのそれ、ただの宅呑みよ、宅呑み!」
「そうなんスか? 瑞樹さんがホームパーティーって」
「瑞樹ちゃんか、もー、しょうがないわねー」早苗は言って、けらけらと笑った。「あ、途中で買い出し頼まれてるから、荷物持ち手伝ってねー。もう全然堅苦しいものじゃないんだから、気楽にいきましょ、ほら、あたしだってなんてことない私服でしょ」
「……はぁ」
比奈は拍子抜けしたように返事をした。早苗のボディコンは比奈にとってはカジュアルな服装の分類に入らなかったが、比奈はそれを口に出すことなく飲みこんだ。
「お豆腐と、しらたき……長ネギはあるって言ってたわね……」
道中のスーパーマーケット、早苗はスマートフォンの画面に表示したメモを見ながら、比奈の押すカートの買い物カゴに次々に食材を放り込んでいく。
「お肉、何グラムくらいいるかしら……うーん……よし、アイドルらしく思い切って少なめにして、そのぶんちょっといいおつまみ買うわ!」
早苗はそう言ってすき焼き用牛肉のパックを買い物カゴに放り込んだ。
「アイドルらしくお肉少なめにしたのに、おつまみ増しちゃったら意味ないんじゃないスかね……」
「いいのいいの、細かいことは言いっこなしよ! あ、こっち二割引じゃない! こっちにするわ」
早苗は割引シールのついたパックと、買い物カゴの中のパックを交換した。
比奈は乱雑に放り込まれたカゴの中の食材を並べなおしながら、早苗の買い物をじっと見ていた。
比奈自身もアイドルとして活動することによって、当然ながら、世の中のアイドルにもオフのときがあると自分の身をもって知った。それでも、ステージの上ではあんなに輝いているアイドルが、いま目の前でスーパーマーケットの買い物に悩んでいるギャップには新鮮な違和感があった。
一方の早苗はそんな比奈の心境を知る由もなく、チーズの棚の前でどれを買おうか悩んでいる。
「よーし、つぎはドリンクねー!」
やや高級志向のカマンベールチーズを買い物カゴに加えて、早苗は意気込んでアルコール飲料のコーナーへと闊歩していく。と。
「あ、重くない?」早苗は比奈のほうを振り返った。「あたし、カート押そうか?」
「大丈夫っス」
比奈は首を振った。
「そう? あたし、こう見えて元警官で黒帯も持ってるのよ。年上とか芸歴とかで遠慮しないでね?」
「……了解っス」
比奈は早苗の元警官という肩書に驚きを隠せなかったが、いまはそれ以上尋ねないことにした。
「よーし、じゃんじゃん行くわよー!」
アルコール飲料コーナーにたどり着いた早苗は、カートの買い物カゴにつぎつぎ缶ビールのパッケージを入れていく。
「ちょっ、ちょっとちょっと早苗さん!」
あわてて比奈が早苗に声をかけると、早苗は動きを止め、きょとんとした顔で比奈を見た。
「なに?」
「ちょっと、入れすぎじゃないっスか?」
「そう? いっつもこのくらいよ?」
「いっつもって……」
比奈は詰みこまれたビールの本数を数える。五百ミリリットルのロング缶の六本のパッケージがカゴに二つ。さらに早苗の右手に一つ。
「でも、これ以上は確かに重たくて大変よね。このくらいにしておきましょうか」
早苗はその手のパッケージもカゴの中に入れると、にっこりと微笑んだ。
比奈はなにも言わずに、ずっしりと重くなったカートを押した。
「ごめんねー、重くない?」
「大丈夫っス。それより早苗さんのほうこそ、そんなにたくさん、重いんじゃ……」
「あたしは大丈夫よー、このくらいなら!」
早苗は白い歯を見せて笑う。
二人は買い物を済ませたあと、菜々の自宅までの道中を歩いていた。早苗は比奈の二倍近い重さの荷物を持っている。
「でも、さすがに悪いっス……」
「いーのいーの、たくさん呑むひとがたくさん運ぶから! それに今日は、比奈ちゃんはじめての参加でしょ? ゲスト扱いよ!」
「そうスか……すいません」
ずんずん歩いて行く早苗の後ろについて、比奈も歩く。歩きながら、早苗の姿を見ていた。現役のアイドルが、スーパーの買い物袋を提げて住宅街を闊歩している。再びの日常と非日常が混じる違和感に戸惑いながら、比奈よりも背丈が小さいはずの早苗の後ろ姿は、比奈にとっては自分よりも大きいものに感じられていた。
スーパーから十分程度歩いた、閑静な住宅街の中に、菜々の自宅はあった。
「ここ、スか……」
比奈はその建物を見て、呟いた。
小さな……あまりにも小さな、アパート。
アイドルになりたてのあの日に見た、ファンに囲まれて、ライブではサイリウムの光に包まれる安部菜々――アイドルの住まいとは、とても思えなかった。
「そうよー、二階なの……よいしょっ!」
早苗は大量の荷物を持って、階段を上がっていく。比奈もその後ろに続いた。
「戻ったわよー!」
ドアベルを鳴らして壁ごしに声をあげる早苗。
ドアの向こうから足音が近づいてきて、玄関の扉が開いた。
「おかえりなさいませー!」
菜々が顔を出した。
「連れてきたわよー」
「ありがとうございます、比奈ちゃん、いらっしゃい!」
菜々はにっこりと笑う。そのスマイルはあの日見たアイドルのときのそれだが、服装は当然私服、トレーナーにジーンズ姿だ。
「お招き感謝っス。おじゃまするっス」
比奈は早苗に続いて中へと入る。
「ウサミン星へようこそー」
「ああっ、早苗さん、それはナナのセリフ……あ、比奈ちゃん、くつろいでくださいね」
「あ、ハイ」
比奈は部屋を見渡す。四畳半のワンルーム。中央に丸いちゃぶ台。布団は窓の近くに綺麗に畳まれている。家具や小物は全体にホワイトや淡いピンクでまとめられていた。一角にやや年代物の大きなタンスがひとつ。備え付けか、実家から持ってきたものか。
それで、菜々の住まいは全部だった。
「菜々ちゃーん、ドリンクは冷蔵庫にいれちゃうわよー」
「はーい、あ、お野菜とお肉はこっちにくださーい」
菜々はエプロンをつけて、早苗から食材を受け取っている。
「比奈ちゃんの持ってくれてた袋もこっちにちょうだい」
「あ、ハイ、アタシも仕込みとか、手伝うっスよ」
「あー、いいんですよー!」菜々は比奈に向かって手を振る。「今日ははじめてでお客さんってことで、気を遣わないでくださーい」
「でも……」
菜々に買い物袋を渡した比奈がその場に立ち尽くしていると、菜々は座布団をちゃぶ台の周りに並べ、比奈の両肩に手をかけて、座布団に座らせる。
「お気持ちだけでじゅうぶんです! それにほら、キッチンが小さいので……二人は立てないんです」
言われて、比奈はキッチンをみる。言われれば確かに、二人がそこに立てば、逆に使いづらくなってしまいそうな広さしかなかった。
「あたしが言うのはちょっと変かもしれないけど、ほんとに気を遣わなくていいのよー?」早苗が缶ビールとペットボトルのお茶をちゃぶ台の上に置く。「じゃあ、さっそく乾杯しましょ!」
「えっ、もうっスか? ほかの皆さんは……」
「瑞樹さんも楓さんも、お仕事が終わってからで、楓さんはかなり遅くなるみたいですよ」
菜々が言う。
「ね? 瑞樹ちゃんの予定だとそろそろってきいてるけど、この業界じゃスケジュールが押すこともざらだから、こういうときはお互いに待たないってことにしてるのよ。菜々ちゃん、コップは戸棚?」
「あ、今日はお客さんが多いので、こっちにしてください」
菜々はビニール袋から取り出したプラスチックのクリアカップと油性ペンを早苗に渡す。早苗はクリアカップを三つちゃぶ台に並べてから、自分の分のクリアカップに油性ペンでさらさらとなにかを書き入れた。
「あ、そういうルールなんスね」
「見分けをつけるためよ」
早苗は油性ペンを菜々に回すと、缶ビールのプルタブを起こす。プシュと小気味いい音がして、早苗はフゥー、と嬉しそうな声をあげながら、黄金色のビールをカップに注いだ。
比奈は早苗のクリアカップを見る。クリアカップには滑らかな筆致で『片桐早苗』と書かれていた。ファンには垂涎もののアイドルの直筆サインが、百円ショップで買ったであろうクリアカップに気軽に書き入れられている光景は、ふたたび比奈に新鮮な違和感をもたらした。
油性ペンが比奈の手元へとやってきた。比奈は二人にならって、クリアカップに自分のサインを入れる。しばらく前に考えた、アイドルとして活動する比奈としてのサインだった。
「へぇー、かわいいですね!」
キャラクターのイラストがあしらわれた比奈のサインを見て、菜々が感心したように言う。
「へへ……まだ描きなれないっスけど」
「そのうちサラサラ書けるようになるわよー」早苗はお茶のペットボトルのふたをひねる。「菜々ちゃんはお茶よね。比奈ちゃんは?」
「あ、アタシもお茶で……菜々さんは呑まないんすね」
「なに言ってるのよ比奈ちゃん、十七歳にお酒呑ませたら即タイホよ、タイホ!」早苗は真剣な顔でそう言い、比奈のカップにお茶を注ぐ。「はーい、どうぞー、それじゃ……」
三人はカップを手に持つ。
「おっつかれー!」
「おつかれさまでーす!」
「おつかれさまっス」
こつ、とプラスチックのカップを合わせて、三人は乾杯した。早苗は注いだビールの半分ほどを一口で呑むと、心底幸せそうに「ぷっはー!」と息をついた。
そのとき、菜々の部屋のチャイムが鳴った。
「あ、はーい!」
菜々が玄関へ走っていく。ドアスコープを覗いてから扉を開けると「おじゃまします」と言いながら、瑞樹が入ってきた。
「こんばんはー、あら、比奈ちゃんも来てくれたのね、ふふ、今夜は楽しみましょうねー!」
「あはは、お手柔らかに……お先にいただいてるっス」
比奈は瑞樹に向かって会釈をする。
「やっほー、いまはじめたとこよー、乾杯しちゃったけど」
「あら、じゃあもう一回しなきゃよねー?」
瑞樹は言いながら、細長い紙袋から淡いグリーンの瓶を取り出す。口のところを紫の包み紙と赤い紐で丁寧に包んだ、高級そうな日本酒の瓶だった。
「ちょっと、なにそれ!」
早苗が身を乗り出す。
「うふふ、今日の仕事先のディレクターが差し入れてくれたの。滋賀のすっごくいいお酒よ!」
瑞樹は瓶を顔のあたりまで持ち上げると、ぱちんとウインクした。
「まぁまぁ瑞樹さんも、まずは手を洗ってから、もう一回乾杯しましょう!」
菜々が座布団を薦める。瑞樹は「はーい」と少女のように言い、洗面台へと向かった。
瑞樹は戻ってくると、ジャケットと荷物を置いて、座布団に正座する。
そうして、二度目の乾杯が行われた。
「ふー、美味しかったわー! もう、ロケだと高級なお弁当の前でもアイドルで居なくちゃいけないから、やっぱり誰にも気兼ねしないで食べれるのが一番よね!」
瑞樹はおおかた空になったすき焼きの鍋を前に満足気に言い、ビールを自分のカップに注ぐ。
当初は瑞樹や早苗のカップが空くと比奈が気を遣って注ごうとしていたのだが、瑞樹が気を遣わなくていいと断った。比奈はそれでもはじめのうちは酌をしていたが、やがて考えを改めた。注げば注いだだけ二人が呑んでしまうからだ。
時刻は二十一時を回っていた。カーテンの隙間から見える外はすっかり暗くなっている。
一方で早苗と瑞樹は酔いが回るほどにますます明るくなっていた。
「ねぇ、比奈ちゃんはどう? アイドル、デビューしてみて」
瑞樹は比奈にそう言うと、カマンベールチーズのかけらをつまみ上げて、あーん、と声を出して口に放り込み、幸せそうに味わう。
「なんなのその質問、面接じゃないんだから、もうー」
早苗はそう言ってけらけら笑う。もはやなんでも面白く聞こえるらしい。赤い顔をして、座布団の上でゆらゆらゆれていた。
「どう……っスか」比奈はカップを両手で持って、しばし考える。「……プロダクションのアイドルの皆さん、思ったより優しくて……意外だったっス」
「意外、ですか?」
すき焼きの鍋とカセットコンロを片付け、ちゃぶ台を布巾で拭いていた菜々が比奈のほうを見る。
比奈はうなずいた。
「アタシ……もっと、アイドル同士はピリピリしてるんじゃないかって思ってたっス。その、アイドルはお互いに……その……」
「ライバルとか、敵同士ってことかしら?」
口ごもった比奈の代わりに、瑞樹が続けた。比奈は少し迷ってから、小さく「そうっス」と肯定する。
「ふぅーん?」瑞樹は興味深そうに微笑む。「どうかしらね、菜々ちゃん?」
「はっ、ええっ!? いや、ウサミン星は平和主義なので、ナナはそんな、敵だなんて」
菜々は急にふられてしどろもどろになる。
「そんなふうに考えたら疲れちゃうわよー?」
早苗はミックスナッツの缶からマカダミアナッツを選んで口に放り込む。
「でも、比奈ちゃんの言うことも一理あるわよね。お仕事のパイが増えないなら、アイドルが増えれば増えるほど、私たちはお仕事をもらうのが大変になるわ。でも……」瑞樹はちゃぶ台に頬杖をついて、カーテンのかかった窓のほうを見つめる。「誰かを、てーい! って蹴落としても、私のところに仕事が来るっていうわけでもないのよね」
「そーねぇ、たしかにそうだわ」
早苗はうなずきながら、空になったカップに缶ビールを注ごうとする。缶の残りが少なかったらしく、数センチも注げずに空になってしまった。菜々が冷蔵庫から新しい缶を取り出し、早苗に手渡す。
比奈は真剣な眼で瑞樹を見ていた。瑞樹は続ける。
「適材適所、って言うでしょ? 同じアイドルでも、私と比奈ちゃんのアピールポイントはきっと違うわ。だから争うより、自分のいいところを伸ばしながら支え合うほうが私はいいと思うの。もちろん、競合したところは本気の勝負よ? オーディションで比奈ちゃんと一緒になったら、全力でぶつかるわ!」
瑞樹は強い目で比奈に微笑みかける。それから、ふっと表情を崩す。
「それでもし落選しても、自分の力が足りなかったって考えるの。自分以外の誰かがいなければ、自分が勝てたなんてふうには考えたくない……でもね? アイドルとして……いいえ、アイドルだけじゃない、私はアイドルになる前には局アナをやっていたんだけれど、そのときも、お仕事をたくさんもらえるかどうかは結局……人となりだったわ。アイドルとしてどんなに美しくて、歌が上手くて、お仕事ができても、スタッフや共演者のみんなが一緒にお仕事をしたいと思えるような人じゃないと、どこかで続かなくなってしまうの」
瑞樹の話に、いつのまにか菜々も早苗も、真剣な表情で聞き入っていた。
「『人格だよ。』……ってコトっスか」
「そういうこと! だから、みんなで仲良くお仕事して、楽しくワイワイやるほうがいいのよ! ストレス溜めないほうが、お肌にだってだんぜんいいわ!」
瑞樹は一転して明るく言う。
「……ありがたいお話だったっス。なんだか、ほっとしたっス」
比奈も表情を崩して微笑む。
「なぁにぃー? ひょっとして今日来たときに先輩からシメられると思ってた? もー、そんなわけないでしょー! むしろ悩みとかあったらあたしたちがなんだって聞いちゃうんだから!」
早苗は比奈と腕を組む。
「あ、ずるーい早苗ちゃん、ミズキも混ぜなさーい!」
瑞樹が早苗と反対側の比奈の腕をとった。
「あ、あはは……菜々さん、どうしましょう」
「うんうん、微笑ましくてナナは眼福ですよ!」
比奈が困った顔で助けを求めるが、菜々は嬉しそうに頷くだけだった。
「でも、実際にアイドルをやってて、困ったり迷ったりしたこと、あった?」
瑞樹が比奈に尋ねると、比奈はふっと、ちゃぶ台の上に視線を落とす。
「アタシは」比奈はひとつ呼吸してから続ける。「アタシがいま、アイドルをしてるっていう事実が、まだ実感できてないっス」
すこしのあいだ沈黙が流れて、比奈は続けた。
「アタシはスカウトされてアイドルをすることになったんスけど、その前に、オーディションに応募して、落選してるっス。応募したのは仲間うちの罰ゲームみたいなもので、応募書類も写真も、合格なんて全然狙ってない、適当に作ったものだったっス。けど、落選の薄い封筒が届いたとき、正直アタシはすこしだけ、ショックだったっス」
比奈は座布団に正座する。瑞樹と早苗は比奈に捕まっていた手を離し、両側から比奈を見つめていた。
「なんででしょう。物語のヒロインになり損ねたからっスかね……いまだに、ショックだった理由はわかんないっス。そんなときに、いまのプロデューサーにスカウトされて、そのときは勇気が出なくて断ろうとして、茜ちゃんに背中を押されて、アイドルになったっスけど……落選からワンチャンもらって、物語のヒロインになるチャンスをつかめたはずなのに、今もどうして、アタシなんかがアイドルになれるって思われたのか……」
比奈は困ったような顔で頭を掻く。
「プロデューサーの話だと、アタシを拾い上げようとしてくれた人は、過労で療養中らしくて、今のプロデューサーはそれを引き継いだ立場っス。だからアタシは今も、どうしてアタシをアイドルにしようと思ってくれたのか、アタシのなにがいいって思ってくれたのか、聞くこともできてなくて」
比奈は三人を順に見る。
「一緒に活動してる皆は、一生懸命で、キラキラしてるっス。一方でアタシは、ユニットの中じゃ一番年上なのに、まだアイドルやってる理由も見つけられてないままで……それが悩みっス……情けないっスね、へへ」
「そっかぁー、年上は辛いわよねー」
「ええ、わかるわ」
早苗と瑞樹がうんうんとうなずく。
「ライブに出ればわかるかと思ってたっス。はじめて出たライブはすっごく熱くて、ドキドキしたっスよ。でも……まだ、アタシはどうすればいいか、わからなくて……だから先輩方に聞いてみたいっス。アイドルになるのに、迷ったり悩んだりしたのか、どうして、アイドルになろうって思ったのか」
「どうして、ですか……」
つぶやいたのは菜々だった。真剣な表情で、比奈を見つめ返している。
空気がほんのすこし重たくなった。
「んーっ!」
瑞樹が明るい声で伸びをする。それで、場の雰囲気を破った。
「ねえ、ちょっと、表にでてみない?」
瑞樹は玄関を指さす。
「外……っスか?」
比奈が言うと、瑞樹は大きくうなずいた。
四人は菜々の部屋の玄関からアパートの共用廊下に出る。外はすっかり暗く、秋へと近づく空気が四人の頬をくすぐった。
「過ごしやすい季節になってきたわねー」
早苗が言いながら、共用廊下の欄干にもたれかかる。酔いの回った顔でしなだれる早苗の姿に、比奈は同性ながら強い色気を感じた。
「夜も遅いので、声は小さめにお願いしますね」
菜々があたりの家々を見回して、釘を刺した。
「みんな、ほら、見て」早苗と同じように、欄干に体重を預けた瑞樹が言う。「星がすごく綺麗よ」
夏から秋に変わりゆく夜の空は、綺麗に晴れて、月と星々が輝いていた。
「ほんとっス。月もきれいで、いい天気っスね」
四人はしばし、無言で星空を眺める。
ドラマのワンシーンみたいだと、比奈は思った。
「アイドルに転向するときね」瑞樹が空を見ながら言う。「もちろん悩んだわ。歳のこともそうだけど、転向して本当にやっていけるのか、私は安易な選択をしようとしてるんじゃないかって。人生を棒に振るかもしれないって、怖いとも思った。そのときも、夜空を見上げてたわ」
瑞樹はふふ、とおかしそうに笑ってから、続ける。
「そしたらね、急に吹っ切れたの。宇宙から見下ろしたら、私なんてすごくちっぽけな存在じゃない? 果てしない宇宙の片隅にこの地球はあって、地球には途方もない数の命があって、そんななかのちっぽけな一人にすぎない私が悩んだって、大したことじゃないって。それなら、私は私のやりたいって思ったことに突き進んでみたほうがいいって、思えたのよ」
「あー、なんだか、瑞樹ちゃんらしいわねー」早苗は菜々の部屋から持って出た自分のカップを口に運ぶ。「でも、あたしも同じかな。スカウトされて、警官かアイドルか悩んだけど、自分の人生だから、やってみようって思ったわ。悩むってことは、悩むだけの魅力があるってことじゃない?」
そうして、早苗はカップに残ったビールをぐいと煽ると、にっと笑った。
「理由なんて、自分が納得するためのものにすぎないのかもしれないわ。やってみたいと思ったから、やってみる。私はそうするわ。比奈ちゃんも、せっかくアイドルになったなら、納得がいくまでやってみたらいいんじゃないかしら?」
瑞樹に言われて、比奈は少し考えてから、穏やかな顔で空を見上げる。
「……そうっスね。アタシは……理由を探そうとしすぎてたのかもしれないっス。やってみたい気持ちは確かなんスから、やってみるのがいいかもしれないっスね。なんだか、巻き込まれ系の主人公みたいっスけど」
言って、比奈はへへ、と笑った。
「ううっ、素敵ですね。ナナは感動してしまいました、なんだか最近涙もろくて……」
菜々が目じりを拭いながら嬉しそうに言う。
「十七歳で涙もろいのは、早いんじゃないの?」悪戯心たっぷりに瑞樹が言う。「ねぇ奈々ちゃん、そういえば、ウサミン星ってどっち?」
「えっ!?」菜々は狼狽する。「えっと、あのっ」
「あら、みなさんお揃いで、どうしたんですか?」
階下から声がして、四人はそちらを見る。
ワンピース姿の高垣楓が四人を見上げていた。
「楓ちゃん、待ちくたびれたわよー!」
早苗が手を振る。
「夕涼みで青春してたの。お疲れさま」
「お疲れさまです、楓さん」
「お疲れさまっス」
「ありがとうございます、お待たせしました。青春ですか? どんなお話をしていたのか、気になりますね」
楓は階段を上がってくる。
「青春もいいけど、夜はこれから! 乾杯して呑みなおすわよー!」
早苗がカップを持っていないほうの拳を振り上げる。
「も、もうだいぶ夜も遅いっスけど……みなさん、大丈夫なんスか?」
「あら、みんな明日はオフでしょ? 今夜は朝まで、じゃないの?」
瑞樹は頬に指を当てて微笑む。
「菜々さんは……」
「ナナは大丈夫ですよー、お布団は一つしかありませんけど」
「もちろん強制はしないわよ、都合がよければね。楓ちゃんは大丈夫?」
「ええもちろん、そうなると思っていました。あたりまえ、です」
楓は得意げに、ポーチからあたりめのパックを取り出して見せた。
比奈は深くひとつ息をついて、覚悟を決める。
「わかったっス。先輩たちにお供させていただくっスよ」
「いいじゃない、さぁ、戻って乾杯しましょ!」
そうして、五人は菜々の部屋の中へと戻って行った。
それからしばらく宴は続いた。瑞樹はアンチエイジングと言って少女のように振る舞い、早苗は自分の担当プロデューサーを電話で呼び出そうとして断られ、楓のダジャレは冴えわたっていた。深夜二時を回ったころになって、仕事で疲れていたであろう楓と瑞樹、そして早苗と、力尽きた者から順々に畳の上に横になり、寝息を立てはじめた。
最後には、アルコールを摂っていない菜々と比奈が残った。
菜々は眠る楓たちにそっとブランケットをかけながら、比奈に言う。
「お疲れ様でした。今日は楽しめましたか?」
「はい。誘ってもらって、ほんとによかったっス」
「よかった、比奈ちゃんが楽しめたなら、ナナもとっても嬉しいですよ」
菜々はにっこり笑う。
「そういえば……菜々さんは、どうして、アイドルになったっスか?」
比奈に問われて、早苗にブランケットをかける菜々の手が一瞬止まった。それから、菜々は丁寧に早苗にブランケットをかけたあと、比奈のほうに向かって正座する。
その姿に、比奈も自然と背筋が伸びるような気がした。
「ナナは、ずっとずっとアイドルに憧れていました。……今も、ずっと……」
穏やかな顔で菜々は言い、そこで一点、表情を崩す。
「だから、夢をかなえるため、ウサミン星からニンジンの馬車に乗って、地球にやってきたんです。トップアイドルへの道はまだまだ途中、です! キャハ!」
菜々はそう言ってあざとくピースをして、それからまたもとの穏やかな顔に戻った。
「そろそろ、私たちも休みましょうか」
「……そうっスね。今日はほんとうに、色々おせわになったっス」
比奈はぺこりと頭を下げる。
「いいんですよ、これで比奈ちゃんもウサミン星の仲間です。またなんでも、相談してくださいね!」
菜々は嬉しそうに言って、微笑んだ。
「ん……」
比奈はうっすらと瞼をひらく。ぼやけた顔であたりを見回して、自分が菜々の部屋に居たことを思い出した。
窓の外はまだ薄暗い。左手に握っていたスマートフォンで時間を見る。朝の五時前だった。慣れない環境で眠りが浅かったのかもしれないと比奈は思う。
畳の上に直接横になっていたせいだろうか、身体が固まっているように感じ、比奈は一度身体を起こす。
伸びをしながら、部屋の中を見渡し、比奈はつぶやく。
「……すごい光景っスね」
安部菜々、片桐早苗、川島瑞樹、そして高垣楓。四畳半のそこかしこに、活躍中のアイドルたちが雑魚寝している。
アイドルにならなければ、いやアイドルになっても、そうそう見れるシーンではない。
比奈は寝息を立てている菜々の姿をじっと見つめた。
思い出す。菜々は「今も、ずっと」と言っていた。きっと、そのあとには「夢見ている」という言葉が続く。菜々は今もトップアイドルを夢見ているのだ。アイドルになることが終わりじゃない。アイドルを続けることが、トップアイドルを夢見つづけることが、アイドルとしての輝きになる。果てしない道。
四畳半のアパート生活でも。夢と一緒なら、突き進んでいける。
「きっと、漫画と同じっスね。描いても描いても、どこかたどり着けなくて、もっと描きたくなるっス。理屈じゃなくて、やりたいと思う自分自身が大事なんスね。『夢を追って後悔するなら納得できる。夢を追わなかったことに後悔したくない』スね」
比奈はみんなを起こさないように口の中で小さくささやく。
「どこまで行けるかわからないけど、瑞樹さんの言う通りっス。どんなになっても、この広い宇宙の中の、ちっぽけな自分の人生」
比奈は深く息をついて、それから、ちゃぶ台の上に残っていた自分のプラカップに描いたキャラクターに、そっと指で触れた。
「アタシにどこまでできるのか、行けるところまで、行ってみましょー。……一緒っスよ」比奈は微笑む。「でも今は……『敢えて寝る』っスね」
そうして、比奈は再び、畳に横になった。
・・・END
俺は安部菜々の自宅を訪れていた。
朝一番に片桐早苗を担当している同僚プロデューサーから連絡が入っていた。早苗が菜々の家で深酒をしており、荒木比奈も同席している宴会のようだから、様子を見てきてくれとのことだ。自分で行けと突っぱねたのだが、今日の俺の仕事のルートが菜々の自宅と近いことまで把握されており、別のプロデューサーに心配されたとなれば、早苗も多少は行動を改めるだろうという思惑があるらしい。
結局、後日の何らかの見返りを約束させて、俺は承諾した。
菜々の部屋のベルを鳴らすと、ドアスコープの向こうの光が消え、それからチェーンロックが開かれる音がした。
玄関のドアが開いて、比奈があくび混じりに顔を出す。
「ふ、あぁ……おはようっス、プロデューサー。どうしたっスか? わざわざこんなところまで」
「仕事の途中だよ。片桐早苗の担当プロデューサーに様子を見てきてくれと言われたんだ。みんなは?」
「まだ寝てるっス」
比奈は部屋の奥をちらりと見る。俺は自分の時計を見た。朝の九時半。まだ寝ているということは、昨夜は相当遅くまで盛り上がっていたということか。
「入っても大丈夫か?」
「大丈夫だと思うッスけど、すごい状態っスよ」
俺は比奈のあとに続いて部屋にあがる。
たしかに、すごい状態だった。
部屋の隅に大量の缶ビールの空き缶、中央のちゃぶ台には片付けられていないままのプラカップとツマミの袋、ちゃぶ台を囲うように眠っているアイドルたち。高垣楓に至っては日本酒の瓶を胸に抱いて幸せそうに寝息を立てている。
およそアイドルが見せていい画ではない。
その光景を目にした俺の口から出た感想は、五感に忠実に従ったものだった。
「……酒くさいな」
「ふふ、青春の匂いっすよ」
そう言って笑う比奈。
俺はその表情に違和感を覚えた。
「なにかあったのか? すっきりした顔してるぞ」
「そうっスか?」
比奈は俺のほうを見る。それから、にっと笑って言った。
「修業回が終わったんスよ、きっと」