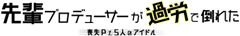
人生はいつも、自分の力だけで思い通りにはできない。なりたいものがあっても、得たいものがあっても、それらが一人の力で手に入れられるということは決してない。ライバルが自分よりすこし優れているだけで。協力者であるはずの人物の力が足りないだけで。その夢はあっけなく崩れる。
目の前にいるこいつらに、この人がプロデューサーじゃなければ夢を掴めたのに。そう思われて終わることだって、ありえないわけじゃない。そのときは潔く、自分が無能であることを受け入れなきゃいけない。
そうじゃなきゃ、目の前のこいつらが力のない無能だってことになってしまう。
そうじゃなきゃ、アイツは力がないのに夢を目指したただの道化になってしまう。
「……そう言うわけで、これからよろしく」
俺がプロデュースするアイドル全員が揃った、初顔合わせの日。美城プロダクションのミーティングルームでユニット活動の概要を伝え、最後にそう挨拶した俺に対して、五人のメンバーはそれぞれの反応を返してきた。
「がんばりましょうっ! いよいよですね! 燃えてきましたーーー走りますか!」
音を立てて椅子から立ち上がったのは茜だった。鼻息荒くしているところを隣の比奈になだめられている。
「茜ちゃん落ち着いて、走らなくていいっス……いやぁ、なんか実際アイドルになるって……実感わかないっスね、まだなんにもしてないっスけど」
比奈は茜の服の裾をひっぱりもう一度椅子に座らせながら、のんびりと言った。比奈は部屋でみたのと同じ、野暮ったいジャージ姿だ。アイドルっぽさのかけらもない。
「私……皆さんに迷惑だけはかけないようにしないと……」
白菊ほたるは、両手を胸の前でぎゅっと握りしめ、足元のあたりに視線を落として、不安そうにしている。
「まぁまぁみなさん……とりあえず、お近づきの印と、ユニット活動開始を記念して、眼鏡どうぞ!」
上条春菜は立ち上がると、カバンから次々に眼鏡を取り出し、その場にいる全員の前にひとつずつ並べていく。色や形が違う。メンバーに合わせて選んできたのだろうか……俺の分もあった。
「ちょっと、待ってよ」
すこしとげのある声がして、眼鏡を配る春菜の手が止まった。部屋の全員が声の主のほうを見る。関裕美が、真剣な眼で俺を見ていた。
「いきなりプロデューサー交代って言われても、納得できない。私のことをスカウトした人は、どこにいっちゃったの?」
「あー、っと、その、怒らないでほしいんだが」
「怒ってない」
裕美は俺の声を遮るように言った。言ってから、俺のほうを見ていた目を逸らす。唇をぎゅっと閉じて、怒りとも哀しみともつかない表情で壁のほうを見つめていた。
ほかのメンバーは不安そうな顔でこちらを見ていた。茜はどうしたらいいのかわからないらしく、俺と裕美とを交互に見て困っている。
「……もともとお前たちをプロデュースする予定だった先輩は、過労で倒れた。だから、俺が引き継ぐことになったんだ。急ですまないが――」
「か、過労……」ほたるが消え入りそうな声で言う。「……やっぱり私が、いるから……」
裕美とほたるを中心に、ミーティングルームには重い空気が流れ出す。俺は困惑した。裕美が先輩の不在で不安なのはわかる。が、ほたるはどうして必要以上に沈んでいるのか。
「いや、だからその」俺は明るい声を作るように努めた。「先輩に比べたら力不足かもしれない。けれど、先輩が戻るまでのあいだは、きっちりやるつもりだから」
俺は記憶を探った。先輩ならこういうときにどう言っただろうか。俺がプロデュースするから、安心しろ、だったか。
「――だから、俺がプロデュースするから、みんな」アイツの顔がちらつく。「一緒に、がんばろう」
ほんのすこし、沈黙が流れた。
「そっか……病気じゃ、しょうがないよね」
裕美はそう言って、目を細めて小さなためいきをついた。笑顔ではなかった。
「そうっスね、まー、やってみましょーか。アタシ、アイドルとかどうすればいいのかわからないっスけど……やってみないと、なにも始まらないですし、やりはじめればどうにか形にはできるもんスよ」
比奈が助け舟を入れてくれる。
「そーです!」
茜が再び立ち上がる。ほたるがそれに驚いたのか、小さく悲鳴を上げた。
「ピンチにこそチームワークを発揮して乗り切るときですよ! ここにいるみんなならできます! メンバー一同頑張りましょう! ファイトーーーーォォォ……あれ?」
いつものシャウトが来るかと思いきや、そこで茜は首をかしげる。
「このチームの名前、なんて言うんですか?」
「そういえば、ユニット名、聞かされてないですね」
春菜が思い出したように言った。気が付くと、さっきとちがう眼鏡をかけている。
「ああ、ユニット名は……まだ未定だ」
「……未定スか」
比奈に確認されて、俺は頷いた。
先輩の残した資料に、ユニット名は書かれていなかった。俺が茜をスカウトするより前、メンバーが決まりきってない段階の資料だったから、最後の一人をスカウトしてからつけるつもりだったのかもしれない。
引き継いだ身として一応ユニット名を考えてはみたものの、あまりしっくりくるものが思いつかなかった。そもそも俺は名づけなんてしたこともない。下手に触るよりかは、先輩が戻るまで未定にしておくほうがいいようにも思えた。
「曲のリリースまでには決まるさ」
俺はそう言い訳する。『決める』ではなく『決まる』という表現を使ったのは、ユニット名は必ずしもプロデューサーが決めるものではないからだ。ユニットメンバーの中から出ることもあれば、誰かお偉いさんがつけることもある。
「うーん、いろいろ宙ぶらりんっスね……はは」比奈が乾いた笑いを発した。「それで、次の予定は、資料によると……宣材の写真撮影、っスか?」
「ああ。このあとはスタジオで撮影だ。実際に活動を始めたほうが、あれこれ悩むより掴めるだろう。俺も先輩から引き継いだばかりでイメージ不足だ。みんなも不安だろうが、一歩一歩やっていこう」
自分を落ち着かせるように、俺はそう口にした。
「センザイ! 洗うんですか! 任せてください! マネージャーですから、みんなのユニフォームだってよく洗ってますよ!」
茜のおそらく本気の間違いは、勢いがありすぎて誰も訂正できなかった。
「おお」
着替えとメイクを終えてスタジオに入ってきた五人を見て、俺は声を漏らした。春菜、ほたる、裕美の三人はユニット結成前に撮ったソロの宣材写真があり、俺も目を通している。そのイメージと大きな差はないが、衣装も違うし、写真で見るのと実際に見るのとでは印象が違う。春菜は姿勢がよいせいか、写真よりも清楚なイメージだ。ほたるはやや暗めのコーディネートにしているにも関わらず、スタジオの照明の効果でネガティブなイメージは払拭され繊細なイメージを得ている。あとは表情が明るくなればより魅力を増すだろう。裕美もドレスを身に纏うことによって、広く見せた額が動的なイメージを作り出し、コサージュもよく似合っている。
比奈はそもそも普段の姿とのギャップが大きく、衣装をまとうだけで化けるが、メイクによって一層映えた。五人の中で最年長だからか、スタイリストも全体的に大人っぽさを強調させることを意識したようだ。一方でヘアメイクは敢えて隙をのこし、本人の無防備さ、無頓着さを素朴な色気に転換している。
茜はというと、顔を真っ赤にして、お腹のあたりを腕で隠すように抱えていた。スタイリストが選んだのはホットパンツとショート丈トップスのへそ出しファッションだった。大きなリボンで長い髪を結び、髪の先はもとからの癖をさらに強調するようにアレンジしている。本人があれだけエネルギッシュなら、順当なコーディネートだ。
「プロデューサー! その……お腹がすーすーします!」
「暖房つけるか?」
「そういうことじゃないと思うっスよ」
比奈が苦笑いした。
カメラマンによる撮影が始まってからは、基本的に俺は見ているだけだ。俺自身もユニットのイメージをつかみ切れていないので、写真についてはカメラマンの感覚に任せている。衣装とアイドルが映えるように撮ってもらえればいい。素人が口を出すよりいいものができあがるだろう。
春菜、ほたる、裕美の三人の撮影は、三人ともすでに経験があって順調だった。続いて比奈の撮影に移る。
「い、痛いっス……これ以上は……無理っスよ……」
「もうちょい頑張って、もうすこし深くしたほうが一番いい角度になるから!」
「う、うぐぐぐ……これで……どうっスか……?」
カメラマンのリクエストに、比奈はポーズの腰の角度をさらに深くする。インドア生活で運動不足なのだろう。カメラマンの指示したポーズを維持するのがものすごく辛そうだ。
「オッケー、それで笑って!」
「無理っス! 心も体も折れるっス! アタシ、スタンド使いとかじゃないっス!」
撮影が終わった頃には、比奈はチェアーでぐったりしていた。
次は茜の撮影だ。
「うん、いいよ、もっとポーズに勢いつけてみようか!」
「勢いですね! こうですか!?」
「あー実際に動いたらブレちゃうから、止まって、止まって!」
「はい!」
「でも勢いはつけて」
「はい!」
「あはは、だから動いたらブレちゃうって! あははは、じゃあもうそれでいいや、気合入れて!」
「ボンバーッ!」
「はいボンバー! あははは」
茜のキャラクターは妙にカメラマンの笑いのツボに入ったらしい。素人である茜の撮影がカメラマンにとってのストレスにならなかったことが幸いだった。茜は撮り終わった写真を見せられながら、カメラマンからかわいいと褒められて顔を真っ赤にしてスタジオを走り回っていた。
最後には五人そろっての写真を撮る。ぜひ全員眼鏡でとねだる春菜のリクエストで、眼鏡で記念撮影のように一枚。これにはなぜか俺も巻き込まれた。その後はアイドルだけで撮影が続いた。比奈が「若いコに囲まれて複雑な気分っス」とぼやき、茜は自分よりも年少である裕美とほたるの二人と並んだときに「もう少し背が高くなりたいです! 牛乳飲みます!」と意気込んでいた。
撮影後は、それぞれ普段着に戻り、五人に初心者向けの一眼レフカメラを一台渡して、プロダクションの内部を使ってお互いの写真を自由に撮らせた。特にルールは設けずに、社内のカフェや団らんスペースでおしゃべりをしながら日常的な表情を撮る。先輩がやっていた手法で、アイドルたちの親睦を深めながら、キャラクターを把握するのによい手段なのだろうと、俺は理解していた。
撮影の日が終わり、プロデューサールームの俺のデスクの一角には、ユニットのアイドルたちの写真をスライドショーするデジタルフォトフレームが増えた。
それから日を置いて、ダンスレッスンがはじまった。春菜、ほたる、裕美の三人は、プロダクションのアイドルイベントにバックダンサーとして参加する予定が入っている。それに合わせて、茜と比奈もレッスンに参加し、基礎のステップから順に慣れていってもらう。
「それでは、まずは曲のあたまからやってみましょう」
トレーナーが五人の前に立ち、手拍子をはじめる。カウントのあとに、五人それぞれがステップをはじめた。春菜、ほたる、裕美の三人は本番も近いので、ダンスはほぼ完成した状態だ。それぞれに細かく指摘すべき点はあるのだろうが、バックダンサーということであれば、現状でもステージで十分通用する。ここからのレッスンは確認と反復練習が中心だ。
いっぽうの茜と比奈は今回の参加が初めての本格的なダンスレッスンということになる。事前に資料を渡して振付を覚えるように伝えてあり、二人とも自宅で練習していたようだ。しかし本番やそれを想定したスタジオのレッスンのような環境は、個人練習とはまったく状況が異なる。ただ振付を覚えればよいというものではない。
レッスンから二十分も経たないうちに、比奈は床にすわりこみ、茜もびっしょり汗をかいている。
トレーナーは最後に茜と比奈の二人だけを残し、それぞれのダンスの状態を見た後に、最初の休憩の判断を入れる。
「お疲れ様です! お水、しっかり摂ったほうがいいですよ!」
春菜が茜と比奈に水の入ったペットボトルを渡していく。レッスン室の端の机に俺が用意していたものだ。
「ありがとうっ、ございます」
「……ありがとうっス」
二人は肩で息をしながらそれを受け取った。春菜たち三人は体力もまだ余裕が見える。
トレーナーはクリップボードにメモを取りながら、二人にレッスンのフィードバックをしていく。
「荒木さんは基礎体力からですね。あとでメニューを作ってプロデューサーに渡しておきます。体力をつけるのは時間がかかりますから、これから毎日着実にがんばって行きましょう」
「了解っス……いやぁ、激しいっスね、アイドル……明日は確実に筋肉痛っス……」
「体力がつくと、身体を動かすのも楽しくなりますよ!」
トレーナーはにっこり笑う。
「あはは、まぶしいっスね……」
「それで、つぎは日野さんですね」
「はい、っ……」茜の返事は詰まり、茜は一つ咳こんだあとに返事をしなおす。「はい!」
「茜ちゃんも思ったより疲れてるみたいっスね、体力ありそうなのに、アイドル恐るべし」
比奈がそう言って水を口に含む。
「頑張りが足りないですかね……もっと走り込みを増やします……!」
「茜ちゃんでそんなになら、アタシはまだまだ遠そうっスね……」
「あまり心配しなくても大丈夫ですよ」トレーナーがフォローに入る。「日野さんは運動部だけあって、基礎的な体力は大丈夫だと思います。いま疲れてしまうのは、振り付けを覚えきっていなかったり、周りのメンバーの動きとのズレに惑わされてしまうからですね。不必要に大きな動きをしたり、呼吸が整わなかったりして、余計に疲れてしまうんです。振付が身について、みんなと一緒に踊ることに慣れれば、疲れすぎずに踊れますよ」
「なるほどっ! がんばります!」
茜は嬉しそうに握り拳を作った。
トレーナーがこちらに歩いてくる。
「お疲れ様です」
「お疲れ様です……どんな感じですか?」
俺が尋ねると、トレーナーは笑顔のまま一つ頷いた。
「ええ、上条さん、白菊さん、関さんの三人は問題ないでしょう、ほかのバックダンサーのメンバーとの調整も時間はかからないと思います。日野さんと荒木さんも、筋はいいですよ。日野さんは動きが大きくなりがちなので、ユニットダンスでは周りに合わせてもらうようにレッスンしていきます。荒木さんは体力が課題ですが、ダンス自体はしっかり覚えてますし、自分の動きをしっかり見ながら練習できているみたいです」
「なるほど」
ひとまず心配することはなさそうだった。比奈はマンガを描いていた経験が美的センスとして応用できているのだろうか。なにが活きるかわからないものだと俺は思う。
「うーん、思ったよりもハードなものだったんスねえ……」
比奈がこちらに歩いてきていた。豊かな髪に汗がキラキラ光っている。
「そこらのスポーツなんかよりはずっと、体力を使うな」
「自信なくなってきたっス……」
比奈は肩を落とす。その目はダンススタジオ中央で、小さな動きでダンスを確認している茜を見詰めていた。茜は短時間の休憩でも体力が回復してきたようだ。
アイドルのステージは見た目の華やかさに反し、実際には体力勝負だ。衣装を着て歌いながら激しいダンス、それを何曲も続けていく。さらに全プログラムを通して笑顔を保ったままで続けなくてはならない。ツアーとなれば連日だ。体力的に限界が訪れていても、たとえステージ中にけがをしていても、アイドルは苦痛に歪んだ顔を決してステージでは見せない。
だからこそ華やかさを保てる。羨望の的にもなれる。
「トレーナーも言ってた通り、こればかりは一朝一夕では身につかないさ。毎日頑張れよ」
「マンガもすぐに上手くなるもんじゃないですし、わかってるんスけどね……うう、引きこもりには厳しいっス……」
比奈は自分の太ももを揉みながら、うめき声をあげていた。
そのあとも数十分、レッスンは順調に続いた。
その日以降、メンバーばらばらに数回のダンスレッスンと、合間を縫ってのボイストレーニングを経て、春菜、裕美、ほたるがバックダンサーを務めるイベントの本番の日が訪れた。
現場は中規模程度のライブステージ。エンタメ系の大規模展示会の中のイベントステージという位置づけだ。
特に出番があるわけではないが、ステージを見学させておくために、茜と比奈も現場に呼んでいる。
「それでは、行ってきますね!」
ステージ裏、衣装に着替えた春菜が、舞台袖の隅にいる俺たちに笑いかける。比奈が軽く手を振り返し、茜はがんばってください、と本人なりに抑えた声でエールを送っていた。
今日はユニットとしての活動ではなく、仕切りもメインのアイドルのプロデューサーだ。春菜たちもほかのバックダンサーとともに行動している。
「笑顔、笑顔……だいじょうぶ」
裕美が胸に手を当ててつぶやいている。緊張しているのかもしれない。
ほたるも不安そうな顔をしている。ダンスは丁寧すぎるくらいに練習していたので心配ないとは思うのだが。
「舞台裏……初めて入ったっス。こういう風になってるんスね……」
比奈はあたりを眺める。
「裏から見ると、表とは全然違うんですね! こう、木! っていうんでしょうか!」
茜がセットの裏側を見て言った。
確かに、舞台裏には独特の雰囲気がある。表側の華やかな雰囲気とは違い、装飾されていない側の無骨な木材、鉄筋と、機材のケーブル、照明。客席やステージ上とは対称的な静けさ。音はステージのセットに遮られ、こちらと向こうが別世界であることを無意識にも実感する。
そして、伝わってくるスタッフたちの緊張感。ここは、舞台という異空間を支える、あらゆる専門家たちの戦場だ。
「……よく見ておくっス」比奈が真剣な顔になっていた。「きっと、貴重な機会っス」
「おいおい、そのうち出る側だぞ」
「そうっスけど……いまのこの新鮮な気持ちはきっと今だけっス」
比奈はそう言って、薄く笑った。――ぞくりとさせられる。
「確かに、比奈さんのいう通り……なんだかすごいですね」
茜も、なにかに憑かれたようにステージのほうを見ていた。
「みなさん、今日はおねがいしまーす!」
高い声がひびいて、俺たちはそちらを注目た。うさぎの耳をつけたアイドルが、バックダンサーたちに頭を下げて挨拶をしている。よろしくおねがいします、とバックダンサーたちの挨拶が返った。
「あの人が、今日の主役なんですね!」
茜がきらきらした視線を向けていた。
「ああ、安部菜々。けっこうキャリアの長いアイドルだ」
「あれ? あのヒト、プロダクションの中で見た気がするっス」
「カフェじゃないか? プロモーションも兼ねて働いてるって聞いた気がするな」
「カフェ……たぶんそうっス」
「そうなんですか! 何歳なんですか?」
「十七歳だ」
「え? プロデューサー、さすがに十七歳は」
「十七歳だ」俺は比奈の言葉を遮った。「安部菜々は十七歳だ」
「……了解っス」
会話をしていると、安部菜々がこちらに歩いてくる。
「安部、菜々です! 今日はよろしくお願いします!」
安部菜々はそう言って丁寧に深く頭を下げた。うさ耳がその動きに追従する。
「いや、俺たちはスタッフではなく、今日は見学で。美城プロダクションの新人のアイドルの現場見学なんです」
俺は両隣に立っている茜と比奈を示す。
「日野茜です! よろしくお願いします!」
「荒木比奈っス。ステージ、がんばってくださいっス」
「そうだったんですか! 茜ちゃんに、比奈さん! これからよろしくお願いしますね! それでは!」
安部菜々はにっこり微笑むと、待機位置へと向かって行った。
「すっごくカワイイ人でしたね!」
「オーラすごいっスね……あれが、アイドル……アタシもあんな風に、なれるんでしょーか」
比奈のつぶやきに、俺は返事をしなかった。アイドルとしてきっちりキャラクターを作り、比奈たちを魅せることができる安部菜々ですら、アイドルとしてのトップ層ではない。
ステージ上の音楽が胸を打つほどに大きくなり、スタッフがにわかに騒がしくなった。安部菜々のステージが始まる。
「始まるぞ」
俺が短く言うと、茜と比奈も真剣な表情になった。
スタッフが出演者たちに合図をした直後、ステージと舞台袖とを隔てるカーテンを開く。安部菜々はスタッフとダンサーたちに向かって穏やかな顔で頷いたあと、暗転しているステージへと飛び出していった。
そのあとを、バックダンサーたちが追いかける。
茜が小さく「頑張って」と声に出した。春菜たち三人に向けたのだろう。
「菜っ々でーーーーっす!」
舞台の明転と同時に、高く明るい安部菜々の声がステージに響いた直後、雄たけびのような歓声が返ってくる。曲の前奏が流れた。
「メンバーの入場は終わった、もうすこしステージの近くまで寄ろう」
俺は客席が見えるか見えないかのところ、アイドルたちの背中が見えるあたりまで二人を連れていく。
そこから垣間見えるのは、アイドルしか見ることが許されない景色。
ステージライトと、無数のサイリウムの光の波に照らされ。
音に乗り、歓声と熱気に包まれて。
場の全てのエネルギーが、その中心にいるアイドルへと向けられる。
普通の人生では絶対にたどり着けない夢の世界が、そこに広がっている。
茜と比奈は、声を発することもなく、ただ安部菜々というアイドルのステージに見入っていた。
俺はそこから二歩下がった。二人が少しでもよくステージを見ることができるように。
ステージを見つめる二人を見て――心がちくりと痛んだ。どんなに憧れても。求めても。あそこまでたどり着けないアイドルだっている。
たった一歩の距離、たった一枚の薄い緞帳で遮られたあの向こう側には、才能と運に恵まれた、運命の女神に見初められた者しか、たどり着けない。
たどり着けないものもいる――だから。
プロデューサーなんて、やりたくなかったのに。
俺は目を細めた。同時に、曲が終わり、客席のほうからは再び、歓声の音の波が襲ってくる。
茜と比奈が同時にこちらを向いた。
「……すごいっスね」
比奈が真剣な眼をして言った。ふだんよりゆっくりとした動きで、比奈は自分の頭を掻く。すこし震えているのかもしれなかった。
茜は声すら出せていない。口で、ゆっくりと深く呼吸していた。胸の内の興奮をどう表現したらいいかわからない。そんな表情だった。
「……二人とも、まだ美城プロダクションのアイドルステージは何曲かある。立ち見になるだろうが、客席のほうからも見てみるといい。俺はここに居るから、ステージが終わったらまたここに戻ってきてくれ」
そう言って、客席側へと続く通路を示した。二人は頷くと、客席のほうへと歩いて行く。
俺はその後ろ姿を見送って、それから肩をすくめた。
「先輩、早く……戻ってきてくれませんかね……」
ぼそりと呟いた俺の声は、次の曲のアイドルに向けられた歓声にかき消された。
「お疲れ様でしたーっ!」
イベントをトラブルなく終えた撤収中の会場に、出演者、スタッフ全員の声が響く。これ以降はスタッフは資材の片づけへ、出番が終わったアイドルはそれぞれに解散となる。打ち上げがあるにはあるが、各個人の事情を考慮して、出席が必須というわけではない。
各所に挨拶を終えた春菜、裕美、ほたるの三人が、俺と茜と比奈のいるあたりへやってくる。
「みんな、お疲れ様」
「お疲れ様です!」
「お疲れ様」
「お疲れ様でした……」
声をかけた俺に、三人が三様に返事を返してくる。
「ふう、無事に終わって、よかった……」
「ええ、本当に……事故もなにもなくて、よかったです」
裕美とほたるが穏やかな笑顔で安堵の息をついた。
「二人とも、すっごくかわいかったですよ! キラキラしてました!」
「そう? ……ありがとう。ちょっと自信、ついたかな」
「ありがとうございます」
茜が目を輝かせて二人を褒めると、裕美とほたるは恥ずかしそうに笑った。ステージのあとは、緊張からの解放と、肉体の疲労とで、格別の充実感が得られる。
「私はちょっとだけ失敗しちゃって……つぎはもっと頑張らないと」
春菜は胸の前で握り拳を作った。失敗があったということだが、とくにショックを受けているわけではないようだ。
「ぜんぜん気づかなかったっスよ、お客さんも気づいてないと思うっス。マンガも展開が熱ければちょっとくらいおかしくったってどうにかなりますし」
「そうだといいんですけどね……」
比奈のフォローに、春菜は苦笑いした。
「おおおーーっ! 私! 燃えてきました! あれがアイドルなんですね! キラキラして、みんなを熱くして……すごいです! その……すごかったんです!」
「あはは、茜ちゃん、さっきから興奮しすぎちゃって、ずっとこんな感じでして」比奈が春菜たちに説明する。「けれど、アタシも興奮したっス」
「つぎは、この五人でステージに立ちましょうね!」
春菜がにっこり微笑んだ。比奈は頷く。
「はいっ! 私も、やりますよぉーーっ! ファイヤーーーーッ!」
茜は拳を天井へ向かって突き上げて、周りが注目するほどの大きな声で雄たけびを挙げた。
「……アイドルのライブ、初めてちゃんと見たっス」
比奈が俺のとなりへと歩いてくる。興奮しっぱなしの茜のほうを眺めながら、比奈はつづけた。
「引きこもってたアタシでも、リア充の世界に、あの舞台に立てるのか……わからないっスけど、ちょっと、興味出てきたっス。なんだか……すっごく熱いマンガ読んだときと似てるっスね、なにかしたくて、いてもたってもいられなくなる感じっス」
「……そうか」俺は比奈の横顔を見た。「良かった」
「でも、プロデューサーは、あのステージを見ても、辞めたいって思っちゃうんスね」
「……」
俺は沈黙した。比奈はこちらを見はしなかった。
「慣れっスかね……マンガも、ある時を境にぱったり描かなくなっちゃう人はいるっス。みんな最初は、熱を持ってたはずなんスけどね。どこに置いてきちゃうのか……アタシは少なくとも、さっき感じた熱さはもう少し、追いかけてみるっスよ。今はプロデュース、おねがいするっス」
「……ああ」
俺の返事を聞いて、比奈はひとつ頷くと、また茜たちのほうへ歩いて行った。
茜は両手に裕美とほたるそれぞれの手をとって、天井に向かって掲げると、大きな声でいつものシャウトをしていた。その不安の欠片も持っていないような、突き抜けた明るい声と表情に、俺は思わず目を細めた。
その数日後。俺は上司から、過労で倒れた先輩の容態が悪く、復帰には時間がかかることを伝えられることになった。
・・・END