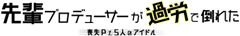
「完璧にやろうとすると固くなる。失敗の数は場数の証だ。恐れずベストを尽くしてこい」
リハーサルを終えた楽屋の中。俺は言いながら、前に並んだ日野茜、荒木比奈、上条春菜、関裕美、白菊ほたるの五人の顔を順に見て行く。
この言葉は先輩の受け売りだった。事務方の俺にも、ライブに立つアイドルたちにも、先輩はそう言って、現場へと送り出していた。
俺は意識的に、少し表情を崩す。
「……その……なんだ、せっかくのライブだ。緊張するより楽しんできてくれ」
「はいっ!」
五人の元気な声が返ってきた。それぞれに緊張も見え隠れするが、表情は悪くない。
今日は美城プロダクションを挙げての一大イベント、サマーフェスの当日。
茜たち五人のユニットが、ユニットとして初めてそろってステージに立つ日だった。
当日までの経過は順調だった。レッスンを重ねて茜と比奈のダンスも一定の水準に達し、五人の宣伝活動はラジオ、雑誌、インターネット配信番組など、規模は小さいが着実に重ねていった。有名な記者にも小さな記事ながら取り上げてもらった。取材終了後、ハンチング帽の下、眼鏡のレンズ向こうから笑顔をのぞかせ、期待していると褒めてもらったとき、五人がとても喜んでいたことが記憶に残っている。
サマーフェスでの茜たちの出番はオープニングの全体演目と、中盤での出演者のトーク、そしてフィナーレの全体演目だ。ユニットとしても楽曲はリリース前、個人としてもまだソロ楽曲を持っていない五人であり、特に茜と比奈はライブへの出場そのものが初体験だ。まずはここでライブに慣れること、ユニットでの楽曲リリースの告知が狙いとなる。
「うううっ! ついに! やってきましたねっ!」
楽屋の中、ステージ衣装に着替えた茜が言う。
ステージ衣装はオレンジをベースカラーにした、夏らしいさわやかなデザインで、アイドルによって細かくアレンジされている。
興奮しエネルギーの行き場がないのか、茜は腕を振り回しながら歩き回っている。
「茜ちゃん、あんまりはしゃぐと本番前にばてちゃうんじゃないですか?」
椅子に座った春菜が笑う。今日の眼鏡はステージでの見栄えを意識したのか、ピンマイクやイヤホンモニターと併せてサイバーなヘッドセットのようにも見える、白く流線形のぶ厚いフレームのものを用意したようだ。
「茜ちゃんはちょっと発散するくらいのほうがいいかもしれないっスね」
同じく椅子に座っている比奈が笑顔で言った。その表情は穏やかで、あまり緊張はしていないようだ。即売会なんかを通して人前に出ることは慣れているのかもしれない。
「そーですっ! この熱い気持ち、止まれませんっ!」
茜は言いながら、ダンス冒頭の動きをする。
「でも、狭いところであまり激しく動きすぎて、ケガ、しないようにしてくださいね……」
ほたるは穏やかに微笑んで、茜を制した。茜はそれでようやく動きを止め、椅子に着くと、楽屋に用意されているペットボトルの水をぐいとあおった。
「とうとう、ここまで来たんだね、私たち」
裕美もまた穏やかに微笑んで、感慨深げに言った。これまでで、五人はユニットの仕事に取り組み、お互いの絆も深まってきている。聞けば、ときどきプライベートで遊びにいくこともあるらしい。
「新しいプロデューサーのおかげ、かな」
はにかみ笑顔で裕美が言った。珍しい素直な態度に、俺もくすぐったくなる。
「今日は大きな舞台だが、レッスンは着実にものにしてきた。心配することはないだろう。がんばってな」
もう一度声をかける。五人は良い顔で頷いた。
俺は五人にステージの様子を見てくると告げて、楽屋を離れた。
今日の資料は頭に入っているし、一度訪れたことのある会場だが、それでも実際に茜たちが通るルートを再度確認しておく。楽屋から廊下を伝って下手側の舞台袖へ。待機しているスタッフたちに挨拶する。
オープニング楽曲での茜たちの入場は二階に組まれたバルコニーだ。バルコニーに複数ある門のような入場ゲートからは、それぞれ今日のフェスで目玉となるアイドルが登場する。その両側に、茜たち新人アイドルが二人ずつついて三人一組で入場する流れだ。階段を上ってゲートへ。自分が待機できる場所を確認する。それから、バルコニーから、まだ空っぽの客席を眺める。
目のまえに広がる二千以上のシートのチケットはほぼ完売。数十分後には、ここは人でいっぱいになる。
「なんとか、ここまで連れてこられたな……」
誰へともなくつぶやき、深く息をついた。先輩が過労で倒れてから数か月、見よう見まねでここまでやってきて、やっと五人をステージに立たせることができた。ここがひとつの区切りと言っていいだろう。
無事にライブが終わったら、今日は普段よりいいビールを買って帰ろう。そんなことを考えながら、俺はバルコニーの階段を降りていく。来た道をもどって楽屋へと戻った。
楽屋の扉を開ける。五人はそれぞれに、自分の衣装やメイクの確認をしていた。おかしなところのない風景に見えるが、俺はなにか違和感を覚えた。
順に五人を見る。違和感の正体が判った。茜が大人しくしている。
茜は楽屋内に置かれた、舞台の様子を確認できるモニターを真剣な眼でじっと見つめて、小さくひらいた口からゆっくりと息をしていた。衣装をまとった胸のあたりがゆっくりと上下している。
「……大丈夫か?」
茜に声をかける。茜は返事をせず、代わりに他の四人が俺と茜のほうを見た。俺は近くまで歩みより、茜の目のまえで手を振る。それでようやく茜ははっとしたようにこちらを見た。
「はっ、ひゃい!」
びくりと肩が跳ねて、間の抜けた声が茜の口から出た。
「茜ちゃん、大丈夫スか? ぼーっとして」
比奈が心配そうに尋ねる。
「あっ、はいっ!」茜は勢いよく立ち上がる。「すいません! 気が抜けてたようです! 大丈夫ですっ! このとおり!」
「ひょっとして、緊張してきたか?」
俺は大きく腕を振り回して元気をアピールしている茜に尋ねる。
大きな舞台となれば、多かれ少なかれ人は緊張する。場数を踏んだアイドルであっても、ライブ当日となればリハーサルと完全に同じ気分では過ごせないものだ。むしろ適度な緊張感は本番の集中力を高めてくれるものだし、緊張が原因で多少のミスがあったところで大勢に影響することはほとんどない。それだけのレッスンを重ねてもいる。
だが、ごくまれに極度の緊張、過呼吸などでアイドルが出演不可能な状態に陥ってしまう場合はある。俺は念のために茜の様子を観察した。
「いやっ、大丈夫です! ちょっと精神を統一していました!」
茜はさきほどまでの呆けた顔が嘘であるかのように、戦意たっぷりの目でこちらを見た。その顔、髪の生え際を中心に、普段より多く、じっとりと汗をかいているように見える。
「……そうか」違和感は晴れなかったが、開演時間も近い。茜がこのまま持ち直すことを俺は祈った。「そろそろ舞台袖に移動しておこう。早めに入ってほかのアイドルを待つくらいのほうが余裕あっていいと思うぞ」
「じゃあ、みなさん、行きましょうか!」
春菜が立ち上がり、楽屋の扉を開く。五人はそれぞれ、真剣な顔で舞台へと向かった。
客席に流れているBGMが小さく聞こえてくる以外はほとんど音のしない、静かな舞台袖に到着する。集合予定時刻まではまだかなりの時間があった。俺たちが一番の到着かと予想していたが、広い舞台袖の中央に、一人の少女がぽつんと立っていた。茜たちと同じ衣装を着ている。ということは、スタッフではなくて同じアイドルだ。
少女がこちらを見た。そこで俺もようやくその少女が誰なのか理解する。無垢な笑顔が魅力的なショートの黒髪。美城プロダクションのアイドル、小日向美穂だ。茜や比奈と同じく、今日のライブが初のステージとなる新人アイドルで、たしか、最初の曲の入場は茜とペアだった。
「小日向美穂です! 今日は、よろしくおねがいします!」
美穂が深く頭を下げる。五人も同じように返事をして頭を下げた。茜の声はその中で飛びぬけて大きい。開演まではBGMを流しているから心配はないと思うが、客が入り始めている客席に聴こえてしまわないか不安になるほどだ。
「私、今日が初めてのライブで……みなさんにご迷惑をかけないよう、いっしょうけんめい頑張りますので、よろしくおねがいします!」
「美穂ちゃん! 今日はがんばりましょう!」茜が嬉しそうに言った。「おたがい初めてどうし! 記念すべき第一歩です! ボンバー!」
腕を振り上げる茜。それに驚いたのか、美穂の肩がびくりと跳ねた。
全体曲のレッスンの機会で茜と美穂はすでに打ち解けているようだ。
「アタシも初めてのライブっス。緊張するっスね……お互いはじめてどうし、がんばりましょー」
比奈がゆるく挨拶する。緊張すると言っていたが、固くなっている様子はない。心配はなさそうだった。茜もやや興奮気味だが、一見しておかしな様子はない。春菜、裕美。ほたるの三人は規模の大小はあれどライブは経験している。問題はないだろう。
「まだ余裕はあるから、入場口を確認しておくといいだろう。客席に見えないように気をつけろよ」
俺が言うと、五人と美穂はそれぞれ、自分の入場場所を確認に走った。
そのあいだに、楽屋から舞台袖へと移動してくるアイドルはじわじわと増えた。スタッフたちの緊張感もにわかに高まっている。
バルコニーへ続く階段を見る。茜と美穂が談笑しながら戻ってくるのが見えた。続いて、裕美、ほたる、春菜、比奈の順に戻ってくる。その頃には、袖に待機しているアイドルたちも十五人以上になっていた。
「ぐっもーにーん! えぶりばーでぃー!」
スタッフやアイドルたちの緊張感とは対照的に、能天気な高い声が響く。鼻歌混じりに楽屋口から舞台袖へと入ってきたその声の主は、ショートの金髪碧眼、日本人とフランス人の両親を持つハーフのアイドル、宮本フレデリカだった。フレデリカは今回の目玉アイドルの一人だ。飛びぬけて明るく、いつも緊張感とは無縁なフレデリカのキャラクターは、男女を問わず広い世代に親しまれている。
「おはよーございまーす、今日はよろしくー」
その後ろから、同じく緊張感ゼロで舞台袖に入ってきたのは、銀髪でこちらも同じくショート、キツネのようにシャープでサバサバした雰囲気を身に纏ったアイドル、塩見周子だった。
フレデリカと周子、そして一ノ瀬志希の三人からなる人気ユニット「誘惑イビル」の演目は、今回のライブで盛り上がりのピークのひとつとなるだろう。
フレデリカと周子が入ってきたので、てっきり志希も来るのかと思いきや、二人の後ろから着いてくるものはいなかった。肩透かしを食らったような周りの雰囲気を悟ったのか、フレデリカは集まっているアイドルたちの中心でぱっと右手を挙げる。
「あ、シキちゃんはまだ楽屋で丸まってるんだ~、だいじょーぶ、本番までにはまにあうよー、たぶんだけどねー」
それから、フレデリカはアイドルたちをぐるりと見回してから、茜たちや美穂のほうを見ると「おおっ?」と興味深そうな声をあげた。
「ねえねえ、たしかライブはじめて、じゃなかったっけ? リハーサルで言ってたよね?」
屈託ない笑顔で近づいてくるフレデリカに、茜、比奈、美穂の三人はそれぞれ頭を下げる。
サマーフェスはかなりの参加者があり、全員のスケジュールを完全に合わせることは困難だった。おそらく、茜たちとフレデリカたちは、リハーサル以外に顔を合わせる機会はなかったのだろう。
「日野茜ですっ! 今日が初めてのライブです! よろしくおねがいします!」
「あっ、小日向美穂、です、私も初めてで……よろしくおねがいします」
「荒木比奈っス。アタシも初めてっス」
「宮本フレデリカだよー! 今日はよろしくね、ラビュー!」
フレデリカは三人に向かって手を振る。それから、長いまつげが印象的な大きな目で、三人を見た。
「ねぇねぇ、三人はもう、掛け声決めた?」
「掛け声、ですか……?」
美穂がきょとんとした声をあげる。茜と比奈も不思議そうな顔をしていた。
「そう、ライブがスタートして、ステージに出ていくときの掛け声だよー、アン、ドゥ、トロワー! みたいにねー! もう決めたー?」
「掛け声……聞いたことなかったっスね……」
「決めといたほうがいいよー、あたしは塩見周子。よろしゅー、がんばろーね」言葉とは裏腹に、やる気を表に出す様子がまるでない周子が話に参加してきた。「掛け声はプロダクションの伝統だからねー、好きな食べ物にするといいって聞いたことあるなー、ね、フレちゃん?」
周子は悪戯っぽい目でフレデリカを見る。フレデリカは一瞬驚いたような顔をしたが、すぐに大きく頷いた。
「そう、そうなんだよー、さすがシューコちゃん、良く知ってるよねー! アタシだったらねー、えーっと『ふつう、味の、コロッケー!』かなー?」
走り出すようなポーズをとって言うフレデリカの言葉に、集まっているアイドルの何人かは吹き出し、何人かは肩を震わせて笑いをこらえている。比奈が苦笑いし、茜と美穂はきょとんとしていた。なんだ、ふつう味のコロッケって。
俺も周りのリアクションの理由を知っていた。もちろん、美城プロダクションにそんな伝統はないし、食べ物にするといいなんてこともない。フレデリカと周子の即興の冗談だ。
フレデリカたちに悪気はなく、本番前の緊張を和らげようとしてくれようとしているのだろうが。
「なるほど! 掛け声ですかっ!」それが冗談だとつゆ知らず、茜はそれを真に受ける。「美穂ちゃん、どうしましょう!?」
「えっ? えっと……」美穂は少しのあいだ悩む。「茜ちゃんの好きな食べ物は?」
「私ですか! 私は……カレーです! ということは……『カ、レー、ライス!』ですかね?」
それはちょっと語呂が悪くないか、と意見をする間もなく。
「うんうん、いいと思うよー。じゃあ、本番もがんばろー」
周子はのんびりと言う。その一言で、アイドルたちはまたそれぞれに待機することになった。
「プロデューサー……掛け声、ほんとに伝統なんスか?」
比奈に尋ねられて、俺は首を横に振った。
「やっぱり、そうっスよね……」
比奈は苦笑いしながら、カレーライスの掛け声を繰り返し練習する茜と、それに付き合わされている美穂を眺めていた。
「でも、掛け声があったほうが、ステージへの入りは合わせやすそうですよね」
となりにいたほたるが言う。
「そうだな」
俺はうなずいた。適当に言ったように見えて、フレデリカと周子の二人はきちんと新人アイドルのことを考えている。頼もしい存在だった。
「おっはよーございまーす!」
「ふぁ、おはよー」
はきはきとした元気な声と、対照的に眠たげな声が楽屋口のほうから聴こえてくる。城ヶ崎美嘉と一ノ瀬志希の二人だった。二人の姿を認めたアイドルたちから次々におはようございますの声が返る。城ヶ崎美嘉はカリスマギャルと呼ばれている人気アイドルで、今日のフェスでも全体プログラムではリーダーとなる場面が多い。
二人が俺の横を通り過ぎるとき、ふっと志希が立ち止まり、俺のほうを見た。眠たげだった目が、玩具に興味を示す子猫のようにぱっちりと大きく開かれたかと思うと、志希は俺のほうにかけ寄り、上目づかいで俺を見て、鼻を近づけてくんくんと匂いを嗅ぎ始めた。
一ノ瀬志希はギフテッドと呼ばれ、化学分野、特に匂いの領域に特化した天才的学習能力を持つ。
「やっぱり! キミ、前よりいー匂いするようになった!」
「は?」
俺は意味が判らず、思わずきき返していた。志希は言うだけ言って、呆気にとられている俺に構わず、フレデリカと周子のほうへと小走りにかけていく。
それから、俺の記憶が蘇る。もう数か月以上前だ。先輩に同行したライブにたまたま出演していた志希に、同じように匂いを嗅がれたことがあった。あのときは「単位は出るかなー」と平坦な声で言われたのだったか。
「……あの時の俺の体臭を覚えているのか?」
信じられないと俺は思った。いまと同じ、ほんの一瞬の出来事だ。いくら天才とはいえ、あの短時間で嗅いだ匂いを今日まで覚えていられるなんてことが、ありえるのか?
「集合五分前でーす!」
スタッフの声がかかる。俺は志希に言われたことを思考の外側に追い出した。開演する前に、五人を集めて声をかけておいたほうがいいだろう。
「比奈、ほたる、みんなを集めてくれ」
俺に言われて二人はうなずくと、それぞれ茜、春菜、裕美のいるほうへと向かった。
ほたるはすぐに春菜と裕美を連れてくる。が、比奈が戻ってこない。俺は比奈が向かったほうを見た。
比奈が、こちらに手を振っている。
俺はほたるたち三人とともにそちらへ向かった。そうしてすぐに、比奈が戻ってこなかった理由を知った。
「ハッ、ハッ、ハッ……」
茜が、足元のなにもない場所を見つめたまま、短く呼吸を繰り返している。楽屋で見たのと同じ光景だ。
「茜ちゃん……」
春菜が不安そうな声をあげる。
俺は奥歯を?んだ。
やはり、茜は普段のように振る舞っているように見えて、その実は緊張が極限に達していたのだろう。だが、もう開演時間は迫っている。今更スケジュールを遅らせるわけにもいかない。本当に動けないのなら、茜にはストップをかけ、医者を呼ばなくては。
「プロデューサー!」
比奈に言われて、俺は比奈のほうを見て首を縦に振る。それから、茜のほうへ向き直り――
「っ……! あ……っ!」
どうしてか。
声が、出なかった。
俺は俺自身に対して困惑した。なにが起こっているのかわからなかった。比奈たちユニットのメンバーに囲まれ、待機しているほかのアイドルたちにも囲まれ、俺は茜を目の前にして動くこともできず、喉の奥から細い息だけを漏らしていた。
どうなっているのかわからないまま、とにかく茜の背に手を添えようと、右手を伸ばしたところで、先に比奈たちが茜に駆け寄る。
それぞれが茜の手を取り、肩に手を添えた。
十数秒で、茜の呼吸の間隔は次第にもとの落ち着きを取り戻した。茜の眼から数粒の涙がこぼれ、舞台袖の床板に小さな丸い水の跡を作る。
ほたるが近くのテーブルからタオルをとってくると、茜の涙と汗を丁寧にふき取った。
「っ、はっ、はーーー……ありがとう、ございます」
茜はようやく言葉を発する。裕美に渡されたボトルの水を口に含んで、時間をかけてゆっくりと飲みこみ、それから、茜は比奈たちに向かって微笑んだ。
それから茜は自分の両の頬をぱんぱんと軽く叩くと、両腕でガッツポーズした。
「よおっし! 日野茜、もう大丈夫です! すっごく緊張してますけど! でもみんなのおかげで吹っ切れました! みなさん! お騒がせしましたっ!」
謝る茜に対して、比奈たちはほっとしたような笑顔を見せる。周りで見ていたアイドルたちも、それぞれに安堵の顔を見せた。
「すいませんプロデューサーさん! やっぱり、緊張してたみたいです!」
「ああ」俺は自分の混乱を隠して茜に笑いかける。「初めての大舞台だ、無理もないさ。きつそうだと思ったら正直に言ってくれ」
「はいっ!」茜は大きく頷く。「楽屋のとき、本当はダメでした! でも今は、きっともう大丈夫です! つぎダメになりそうなときは、すぐに言います!」
俺は茜の言葉を信じることにした。冗談は言えないようなやつだ。これならきっと、大丈夫だろう。
俺はもう一度、さっき自分に起こったことを思い出す。どうして、声が出せなかった?
そう考えているあいだに、俺の周りには茜たち五人が集まっていた。俺は再び、思考を中断する。
「よし、それじゃいよいよ本番だ。どんなことでもいい、なにかあったらすぐに相談してくれ。一人で背負わないようにな。記念すべき、初ライブだ。……みんな、頑張ってこい!」
「はいっ!」
五人の声が重なる。
「……閃光のように! ……っス」
比奈が拳を握り締めていた。
「時間です! 集合確認できてます、開演まであと五分!」
「じゃ、円陣組もっか!」
美嘉が声をかけると、アイドルたちは並んで輪を作る。美嘉が右手を出すと、それにならってアイドルたちは全員右手を出した。
「掛け声は……」
「やっぱり、美嘉ちゃんにかけてもらうのがいいんじゃないでしょうか」
そう言ったのは、高垣楓。アイドルたちの中で芸歴も長く、本番を前にしても落ち着き払っていて風格がある。
「あはは、楓さんに言われちゃ、しょーがないかな、それじゃ……」
美嘉は一転して、好戦的な獣のように目をぎらつかせる。
すぅ、と息を吸い込んで。
「今日、ここを! 世界の中で一番アッツい場所にする! 美城プロ、サマーフェス! いくよぉっ!」
重ねた手のひらがぐっと沈んだかと思うと、アイドルたちの掛け声とともに、羽ばたくように高く掲げられた。
茜たちとともにバルコニーへ上がるステップをのぼる。バルコニーのゲートの向こうからは開演を待つファンたちの熱気が伝わってくる。暗幕で区切られたゲートの前に、それぞれのアイドルが立った。
比奈と春菜は川島瑞樹の両翼に。裕美とほたるは佐久間まゆの両翼だ。俺は直前の茜の件を受けて、念のために茜の入場位置付近に待機することにした。茜と美穂は、美嘉の両翼となる。
「初めてのライブって、緊張するよねー。アタシも最初の時はヤバかったなー、でも、レッスンの通りやれば大丈夫だから、楽しもうねー、サイッコーの景色だからさ!」
美嘉はそう言って茜と美穂に笑いかける。緊張を感じさせない、軽快な声色だった。
「はいっ! よろしくお願いします!」
「よろしくお願いします」
茜と美穂がそれぞれ返事をすると、三人はゲートの前に立つ。
ほかのゲートも同じように、それぞれのアイドルが並んでいた。
暗幕の向こうにはまだ、開演前のBGMとしてアイドルたちの音源が流れている。増幅された低音が胸を衝く。この時間は、裏方の身とはいえど、緊張しなかったことはない。
「本番、いきます!」
スタッフの声がかかり、BGMがひときわ大きくなる。それに引っ張られるように会場の熱は一層高まり、そしてBGMが消えゆき、ファンの声だけが残る。
ファンファーレが始まる。目の前の三人が、すぐに飛び出せるようにほんの少しだけ姿勢を低くした。
ファンファーレが終わる、その瞬間に、ゲートの暗幕が一斉にあげられる。ステージの向こうの光が飛び込んでくる。
「行くよ」
美嘉が両隣の二人に声をかけた。
「行って来い」
俺はそれぞれのゲートにいる五人に声をかけた。
最初の曲のイントロが始まる。
茜と美穂はスタートの姿勢をとる。
「行きます!」茜が言った。「『カレー!』」
その言葉を聞いた瞬間に、俺の脳はフル回転を余儀なくされた。目の前の景色がゆっくり流れる。きっと、美穂も同じだっただろう。
『カレー』で始めたら、残りは『ライス』しかない。二拍だ。打ち合わせは『カ・レー・ライス』で三拍だったじゃないか。
茜、それじゃあ、タイミングが合わない。
伝えなくては。ストップして、もう一度。変に強行してガタガタになるより、仕切り直したほうがいい。
「ぁ……っ!」
また、だった。
また、俺の喉からは声が出なかった。
胸が、喉が、音を出すのを拒絶するみたいに、俺の言おうとすることを拒む。
どうして。そう考えているあいだに、時間は過ぎる。
「ラ……」
茜もミスに気づいたようだった。茜と美穂はタイミングを逸する。ゲートの手前で、二人はがくん、と姿勢を崩した。茜と美穂の顔が同時にさぁっと青くなる。
「大丈夫っ!」美嘉が二人の頭に手を置く。「今日はうまくいってもいかなくても、アタシたちが主役なんだから、ぜんぶ成功なの! ね!」
そう言って、美嘉は強い瞳で二人を見る。二人の顔に赤みが戻る。
城ヶ崎美香。この一瞬で、ファンだけでなく同じアイドルの心までひとつにする。恐るべきカリスマ。
「はいっ!」
二人の声が揃う。
「もう一回行くよ、いち、に……さん!」
美嘉のかけ声で、茜と美穂の二人は光の中へ飛び込んでいく。その後ろを追って、美嘉もステージへ。
客席からは大歓声が飛んでくる。
俺はほかのゲートも確認する。どのゲートも無事に入場したようだ。すぐに最初の曲のAメロが始まった。
長く息をつく。それから、ゲートの端からステージを覗いた。茜が歌い、踊る姿が見えた。
小さな体で、手足をいっぱいに伸ばして。
あの日、河川敷で俺とぶつかったことから始まったあの少女は。
いま、アイドルになっている。
目の前の景色がにじんで、ぼやける。茜の姿がシルエットのように、不鮮明になった。
自分の涙だった。
「ああ」
それで、気づいてしまった。
自分がどうして、茜に向かって声を出すことができなかったのか。
ぼろぼろこぼれる涙が頬を流れていくのも構わず、俺はゆっくりと、階段を降りて舞台袖一階へと戻った。
ステージを映すモニターの前に行くと、そこには壮年のベテラン社員とちひろさんがいて、アイドルたちの活躍を見守っていた。
壮年社員が俺のほうへと歩み寄ってくる。涙と鼻水の止まらない俺の顔を見ると、穏やかに微笑んで「お疲れさま」と声をかけてくれた。
「ずいません、ごんな……」
こんな顔で、と言いたかったのだが、ちゃんとした声にはならなかった。
「不慣れな仕事で、よく頑張ってくれた。立派だよ、彼女たちがしっかり羽ばたけたのは、キミのおかげだ」
「……」
俺が黙っていると、壮年社員はほーっと、長い息をつく。
「大人はなかなか、満足に泣くこともできやしないんだ。辛いよね。いまは、大丈夫だ」
壮年社員が俺の心の内を知っているとは思えない。それでも俺は、壮年社員の言葉に甘えさせていただくことにした。
「お疲れ様でした、プロデューサーさん」
ちひろさんが俺にドリンクを差し出してくれる。俺は「ありがとうございます」と濁った声で言いながらそれを受け取ると、ドリンクをあおった。
いつもよりも甘く感じた。
ありがたかった。
「あの子たちも、頑張ったなぁ」
モニターを見ながら、壮年社員は感慨深げに言った。
「ええ」
俺はようやく、ハンカチで顔を拭うと、モニターを見つめた。
あまり大きくはないモニターの中には、ほとんど豆粒みたいに見えるアイドルたちが、歓声を浴びて歌い、踊る姿が映されている。
その一角に、大きくエネルギッシュな動きで踊り続ける、背の低いアイドルが一人。日野茜。
俺はその姿をじっと見つめた。
あれは日野茜。俺の幼なじみのアイツじゃあない。
そんな簡単な事実からすら、俺はずっと逃げ続けていたんだ。
アイドルに憧れ続けていた地元の幼なじみは、高校を卒業すると、すぐに上京して、いくつもの事務所のオーディションに応募していた。
一方の俺は、地方の大学に通いながら、イベントスタッフのアルバイトなど、芸能関係の仕事を積み重ねていた。
幼なじみのアイツはアイドルに。俺はそのプロデューサーに。高校を卒業するとき、交わしなおした約束に大した拘束力があると思っていたわけではない。特に将来への展望もなかった俺にとっては、選ぶアルバイトの方向性を絞るいい口実くらいに思っていた。
俺がアルバイトの経験を重ねて少しずつ芸能界の仕事に近づいていく一方、アイツのほうは思わしくなかった。オーディションの落選を繰り返し、ようやく小さなプロダクションに入ったものの、まともな仕事は殆どなかった。とりあっていた連絡は少しずつ間が空くようになった。
アルバイトの経験を買われて入った芸能プロダクションから、更に人間関係を伝って転職し、美城プロダクションへ。俺はいつのまにか、約束を果たしていた。
一方で、約束を果たすことができないまま、アイツの心は折れた。年齢を重ねてもアイドルとしての実績は得られず、それでも芸能界に残ろうとした結果、来る仕事はアダルトまがいのものばかり。そうしてついに、アダルトではないものの、内容の過激なイメージビデオに出演し、その直後に心をすり減らしたアイツは自分で自分の夢に幕を下ろした。
約束を果たせなくて申し訳ないと書かれたメールの受信を最後に連絡は途絶え、アイツは姿を消した。過激なイメージビデオの出演は、人の噂が大好きな田舎の狭いコミュニティには格好の話題であり、地元にも居られなくなったアイツは家族ごとどこかへ引っ越した。
あとには、約束も夢も目標もなくなった俺だけが残った。
俺はモニターを見つめる。
茜たちは歌い、踊り続けている。
俺は茜とアイツを同一視していた。だから、これまでもずっと、そして呼ぶべき大切な場面で、その名前が呼べなかった。
茜とアイツは違う。
茜がステージに立ち、アイツがたどり着けないところへ茜がたどり着くまで、こんな簡単な事実にすら気づけないなんて。そんな失礼なことがあるだろうか。
自己嫌悪しながら、それでもモニターを見つめ続けた。
「助けられてるよねぇ」
壮年社員が、モニターを見つめたままつぶやく。
「私たちはアイドルのみんなを支え、輝く手伝いをしている……でもその実、私たちもこれ以上なく助けられているんだ、彼女たちの、輝きに」
「……はい」
「これからも、頑張ってくれよ、プロデューサー」
「……はい」
「頑張ってくださいね、プロデューサーさん」
「……はいっ」
返事をした自分の声は、自分でも驚くほど、素直だった。
モニターの中では、曲が終わったアイドルたちが、きらきら輝く笑顔で客席に手を振っていた。
それを見つめながら、俺は心のなかで別れを告げる。
幼いころの、約束に。
さようなら。俺は、新しい夢を支えに行くよ。
ライブは続く。
茜、比奈、春菜、裕美、ほたるの五人は中盤のトークコーナーでこれからCDデビュー予定のユニットであることを告知。茜の天然の熱血ボケと、比奈の冷静なツッコミは会場の笑いを誘った。
春菜、裕美、ほたるの三人はほかのアイドルのプログラムの一部にダンサーとして出演。
そしてプログラム最後の曲と、アンコールまでを無事に終えて、サマーフェスは大盛況のうちに終演となった。
長い時間をかけて客席に向かって深い感謝の礼をし、顔をあげた茜たちアイドルの顔は、みんな晴れやかだった。
「おつかれーっ!」
舞台袖に戻るなり、美嘉の声が出演者みんなをねぎらう。アイドルたちがお互いをねぎらう声があちらこちらで響いていた。
「今日はありがとうございました!」
美穂が美嘉に言う。
「すいませんっ、入りを失敗して迷惑をかけてしまいましたっ! 次はもっと合わせやすい食べ物を掛け声にしますっ!」
茜が美嘉に向かって頭を下げる。食べ物の掛け声はやめるつもりはないらしい。
「おつかれさまー! すっごくよかったと思うよ! 失敗なんて気にするほどじゃないからさー。美穂ちゃんはキュートだったし、茜ちゃんは体力すっごいよね! 二人とも、また絶対一緒にライブやろ!」
言いながら、美嘉はにっと笑って茜に向かって拳を突き出す。
茜は一瞬戸惑ったようだが、すぐに自分の拳を出して美嘉と突き合わせた。それから、パンと小気味いい音を立ててお互いの手のひらを打った。
「プロデューサー」
裕美とほたるがこちらに歩いてくる。
「おう、お疲れ様」
「なにも大きな事故がなくて、よかったです……」
ほたるはほっとした顔で笑った。
「終わった……でも、終わりじゃなくて、私たちはここがスタート、だよね?」
裕美に尋ねられ、俺はうなずく。
「ああ」俺は二人の顔を順番に見た。「すまない、裕美、ほたる、それと春菜は、これまでもプロダクションでアイドルとしての活動経験があることに俺自身が甘えてしまって、フォローしきれないことが多かった。これからはユニットでリリースまで頑張ろう。仕事もどんどん増やしていくぞ。よろしくな」
「うん。よろしくね」
裕美は穏やかな笑顔で返事をする。
「お仕事……すみません、よろしくお願いします」
ほたるはどこかに不安そうな色をのこして、だけどもやはり笑顔で返事をしてくれた。
二人は曲で共演したメンバーのところへと歩いて行く。
「プロデューサーさん」
「プロデューサー」
こんどは春菜と比奈が近づいてくる。
「今日のライブは、いつもより会場が輝いて見えた気がします。眼鏡の自分に自信をもってやれたからでしょうか。……ふふ」
春菜はほかの共演者にも挨拶をしたいと言って、すぐにその場を離れた。
「お疲れさん」
俺は残った比奈に声をかける。
「お疲れっス。どーしたんスか? その顔」
比奈は悪戯っぽい目できいてくる。きっと、俺の目の周りは真っ赤になっているのだろう。
「大人はいろいろあるんだよ」
「そっスか」
比奈は俺のとなりに立ち、それ以上は聴いてこなかった。
「……いくら辞めたいとは言っても、お前たちのことはちゃんと責任を持つよ」
「……?」
「この前、聞かれたことの話だ。中途半端にはしないさ」
「ああ」比奈は何のことだかわかったようだった。「いまは、その答えでいいことにしておくっスよ、プロデューサー」
そう言って、比奈は笑った。
「プロデューサー! やりました! ファイヤーッ!」
茜が遠くから大声で言い、太陽みたいな笑顔で、こちらに走ってくる。
茜は俺の前で立ち止まり、興奮冷めやらぬ目で俺を見る。
「ああ」
「ライブ! すごく熱くて! すごく楽しかったです! ぜんぶ、私をスカウトしてくれたプロデューサーのおかげです、ありがとうございました!」
「ああ」
俺は茜の目を見ながら言った。
これからはきちんと、名前を呼ぼう。
「でも、輝いたのはお前や、みんな自身の力だよ。頑張ったな。まずは、お疲れ、……『茜』」
俺の言葉に、茜は少しのあいだだけ目を丸くして。
それから、満面の笑顔で応えた。
「はいっ! お疲れ様でした!」
こうして、美城プロダクションのサマーフェス、茜達の最初の舞台は幕を閉じた。
日野茜、荒木比奈、上条春菜、関裕美、白菊ほたるの五人は、次のステップへ向けて、これからも突き進んでいく。
・・・END
「あ、お疲れです。すいませんご心配かけまして……ええはい、ようやく動けるようになってきました。医者からはもう少し大人しくしてるように言われてるんですけど。……やだなぁ、さすがにこれ以上無茶できないですよ、医者がいいって言うまで大人しくしてます。そんで、全快してからはまた、バリバリやりたいと思ってますんで! それじゃ、また連絡します。ドリンク差し入れしてもらえるの、待ってますよ、ちひろさん!」
ガチャン ツーツーツー